
トップページ > 刑事政策関係刊行物:犯罪白書 > 女性犯罪者の実態と処遇-令和6年版犯罪白書の特集から-
犯罪白書
女性犯罪者の実態と処遇-令和6年版犯罪白書の特集から-
芦沢 和貴
第1 はじめに女性の刑法犯の検挙人員は、平成18年以降減少傾向にあり、令和5年は3万9,370人と、平成17年の約2分の1であった。また、女性入所受刑者の人員は、19年以降減少傾向にあり、令和5年は1,486人と、平成18年の約5分の3であった。このように、女性の刑法犯の検挙人員及び女性入所受刑者の人員はいずれも減少傾向にある。他方、元年以降の女性入所受刑者の再入者率を見ると、3年まで上昇し49.9%となった後、翌年以降低下傾向となり、16年には28.4%まで低下したものの、翌17年から令和元年まで再び上昇傾向に転じ、以降は高止まりの状況にある。
令和5年3月に閣議決定された第二次再犯防止推進計画においては、第一次の同計画に引き続き、犯罪をした者等の特性に応じた効果的な指導の実施等が重点課題として位置付けられている。女性受刑者等に関しては、虐待等の被害体験や性被害による心的外傷、依存症・摂食障害等の精神的な問題を抱えている場合が多いことが指摘されており、具体的施策として、女性の抱える困難に応じた指導・支援が盛り込まれている。したがって、女性犯罪者に対し、その抱えている困難の実態を把握し、傾向や特徴について分析することの必要性は高い。
法務総合研究所では、女性犯罪者に関し、これまでも平成4年版犯罪白書特集「女子と犯罪」、平成25年版犯罪白書特集「女子の犯罪・非行」等において、公的統計に基づいた動向分析等を行ってきたところであるが、いずれも各調査時点から相応の年数が経過している。そこで、女性犯罪者に関する実態把握のためには新たな調査・分析を行うことが重要と考え、令和6年版犯罪白書では「女性犯罪者の実態と処遇」と題して特集を組むこととした。そして、本白書の特集では、近年の社会状況の変化、女性による犯罪の動向、女性犯罪者に対する処遇・支援の現状等を概観するとともに、女性受刑者等を対象とした特別調査を行い、男性受刑者との比較による分析に加えて、女性受刑者の入所罪名の多くを占める窃盗事犯及び薬物事犯という二つの犯罪類型に着目して分析を行った結果から、女性犯罪者の再犯防止及び円滑な社会復帰を図る上で留意すべき点について検討を行った。
本稿では、このうち、まず、女性を取り巻く近年の社会生活の状況や、刑法犯及び特別法犯の検挙人員等の推移など、刑事手続の各段階における女性による犯罪の動向等の一端を取り上げる。その上で、前記特別調査の結果に基づいて明らかにした、近年の女性受刑者の意識や実情に係る傾向・特徴を紹介するとともに、これらを踏まえた女性犯罪者に対する処遇・支援の更なる充実に向けた課題や展望等について述べる(法令名・用語・略称については、特に断りのない限り本白書で用いられたものを使用するほか、元号については、直前の元号と同様である場合は記載を省略する。)。
なお、本稿では、できる限り本特集の概要を紹介することに努めたが、紙幅の関係上割愛した図表・分析結果等を含む本特集の詳細については、本白書を御一読いただきたい(本稿中、本白書の記載を超えるものは、筆者の個人的見解である。)。
第2 女性を取り巻く近年の社会生活の状況
女性を取り巻く近年の社会生活の状況として、まず我が国の総人口について見ると、平成23年以降、13年連続で減少している。令和5年10月1日現在の総人口は1億2,435万2千人であり、総人口を男女別に見ると、女性は6,385万9千人(総人口に占める割合51.4%)と、前年と比べ33万人減少しており、男性は6,049万2千人(同48.6%)と、前年と比べ26万5千人減少している。人口性比(女性100人に対する男性の数をいう。)は94.7であり、女性が男性よりも336万7千人多くなっている。他方、14歳以上の年齢層別人口の推移について見ると、男女共に、14~19歳及び20~29歳の人口はいずれも減少傾向にあるのに対し、65歳以上の人口は平成6年以降増加傾向にあり、令和5年は女性が約2,051万人、男性が約1,571万人と、いずれも平成6年の約2倍であり、高齢化が進んでいる状況にあった。
また、世帯数の総数は、平成10年から増加傾向にあり、令和4年は5,431万世帯であったところ、65歳以上の高齢者の家族形態別構成比の推移について見ると、男女共に、単独世帯及び夫婦のみの世帯の者はいずれも上昇傾向にあるのに対して、子と同居世帯の者は低下傾向にある。同年の単独世帯及び夫婦のみの世帯の者の構成比は、女性ではそれぞれ25.3%、34.8%、男性ではそれぞれ17.2%、47.7%であった。
年齢層別就業率について見ると、男女共に、55~64歳の就業率が上昇しているが、女性はいずれの年齢層においても男性よりも就業率が低く、令和5年では、男性の就業率は25~34歳、35~44歳、45~54歳及び55~64歳のいずれも9割前後であるのに対し、女性の就業率はいずれも7~8割程度となっている。また、雇用形態別構成比について見ると、女性では、「正規」及び「パート・アルバイト」がいずれも40%台であるのに対し、男性では、「正規」が70~80%台を占め、「パート・アルバイト」は10%前後であり、女性の就業状況は男性と比べて不安定であることがうかがえた。
さらに、配偶者及び交際相手からの暴力の被害経験の有無を見ると、身体的暴行、心理的攻撃、経済的圧迫、性的強要のいずれについても、女性は、男性よりも被害経験があると答えた者の構成比が高く、女性は男性と比べて、配偶者及び交際相手からの暴力の被害経験を有する者が多い傾向にあることがうかがえた。
第3 女性による犯罪の動向等
1 刑法犯及び特別法犯の検挙人員等
刑法犯及び特別法犯の検挙人員並びに人口比の推移(最近30年間)を男女別に見ると、図1のとおりである。刑法犯及び特別法犯の検挙人員総数は、女性では平成17年(9万5,760人)、男性では18年(37万4,125人)をピークにその後はいずれも減少傾向にあるところ、令和5年は、女性では4万6,813人、男性では19万3,472人と、いずれもピーク時の約2分の1であった。また、女性は、平成6年以降、一貫して男性よりも刑法犯及び特別法犯の検挙人員総数が少なく、令和5年の男女を合わせた検挙人員総数(24万285人)のうち、女性の占める比率は19.5%と、約5分の1であった。
また、検挙人員の人口比(14歳以上の男女別10万人当たりの検挙人員をいう。)について見ると、女性は、刑法犯では平成17年の147.0、特別法犯では7年の23.1をピークにその後はいずれも低下傾向にあるところ、令和5年の女性人口比は、刑法犯では68.5、特別法犯では13.0と、いずれもピーク時の約2分の1であった。他方、男性は、平
図1 刑法犯・特別法犯 検挙人員・人口比の推移(男女別)
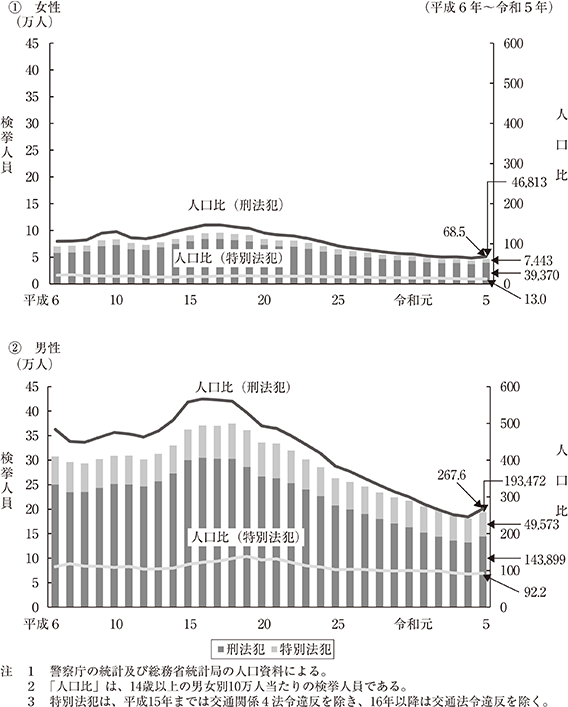
成6年以降、一貫して女性よりも人口比が高く、令和5年の男性人口比は、刑法犯では267.6、特別法犯では92.2であった。
2 窃盗の検挙人員等
刑法犯のうち窃盗の検挙人員について、その推移(最近30年間)を男女別に見ると、女性では平成17年(6万462人)、男性では16年(13万5,023人)に最多を記録したが、その後はいずれも減少傾向にあり、令和5年は、女性では2万6,712人、男性では5万8,823人であった。その刑法犯及び特別法犯の検挙人員総数に占める比率について見ると、同年は、女性では57.1%、男性では30.4%であった。
また、態様・手口別人員について見ると、万引きは、男女共に、平成17年をピークにその後は減少傾向にあるものの、女性では、6年以降、一貫して窃盗の検挙人員の75%以上を占めており、令和5年は75.7%に相当する2万228人であるのに対し、男性では、平成20年以降、窃盗の検挙人員の5割程度を占めるにとどまっており、令和5年は49.6%に相当する2万9,171人であった。このように女性の窃盗事犯においては、万引きが大きな割合を占めていることが男性と比較しての特徴といえる。そして、万引きの微罪処分率(万引きの検挙人員に占める微罪処分により処理された人員の比率をいう。)について見ると、女性は、平成6年以降、一貫して男性よりも高く、令和5年は48.5%と、男性(38.5%)よりも10.0pt 高かったことから、万引きの場合、女性は、男性と比べて、検察官に送致されずに刑事手続を終えることが比較的多い傾向が認められる。
3 薬物事犯の検挙人員等
特別法犯のうち薬物事犯(覚醒剤取締法違反、大麻取締法違反、麻薬取締法違反、あへん法違反、毒劇法違反及び麻薬特例法違反をいう。以下この項において同じ。)の検挙人員について、その推移(最近30年間)を男女別に見ると、男女共に、平成6年(女性6,474人、男性2万3,760人)に最多を記録したが、その後はいずれも減少傾向にあり、令和5年は、女性では1,895人、男性では1万1,551人であった。その刑法犯及び特別法犯の検挙人員総数に占める比率について見る と、同年は、女性では4.0%、男性では6.0%であった。
また、罪名別人員について見ると、女性では、覚醒剤取締法違反が平成9年の3,834人(薬物事犯の検挙人員に占める比率66.5%)をピークにその後は減少傾向にあるものの、7年以降、一貫して最も多く、薬物事犯の検挙人員の5割以上を占めており、令和5年は1,105人(同58.3%)であった。他方、男性では、覚醒剤取締法違反は、平成9年の1万5,857人(同69.6%)をピークにその後は減少傾向にあり、令和4年には薬物事犯の検挙人員に占める比率が5割を下回り、5年は4,622人(同40.0%)と、同年の大麻取締法違反(5,662人(同49.0%))よりも少なかった。このように女性の薬物事犯においては、覚醒剤取締法違反が大きな割合を占めていることが男性と比較しての特徴といえる。
4 起訴人員及び起訴猶予率
検察庁既済事件(過失運転致死傷等及び道交違反を除く。)について、起訴人員及び起訴猶予率の推移(最近20年間)を男女別に見ると、起訴人員総数は、平成16年以降、一貫して男性よりも女性が少ない。このうち、窃盗及び覚醒剤取締法違反の場合、起訴人員において、いずれも一貫して男性よりも女性が少なく、他方、起訴猶予率において、いずれも一貫して男性よりも女性が高いことから、女性は、男性と比べて、起訴に至らず刑事手続を終えることが比較的多い傾向が認められ、この傾向は、令和5年の起訴猶予率の男女差が大きい窃盗(女性60.5%、男性45.9%)でより明らかといえる。
5 入所受刑者・出所受刑者
入所受刑者の人員について、その推移(最近20年間)を男女別に見ると、女性入所受刑者の人員は、平成18年の2,333人をピークに翌年からおおむね横ばいで推移した後、28年からは減少傾向にあり、令和5年は1,486人(前年比68人(4.4%)減)であった。他方、男性入所受刑者の人員は、平成18年の3万699人をピークに翌年から減少しており、令和5年は1万2,599人(前年比307人(2.4%)減)であった。このように女性入所受刑者の人員は、平成16年以降、一貫して男性入所受刑者よりも少ない。また、その年齢層別構成比について見ると、女性入所受刑者では、65歳以上の高齢者の構成比は同年には5.4%であったが、翌年以降上昇傾向が続いており、令和5年は22.7%と、平成16年の約4.2倍であった。他方、男性入所受刑者では、令和5年の65歳以上の高齢者の構成比は13.3%と、平成16年(4.1%)の約3.2倍であった。このように女性入所受刑者の65歳以上の高齢者の構成比は、同年以降、一貫して男性入所受刑者よりも高く、近年も上昇し続けている。
入所受刑者の罪名別人員の推移(最近20年間)を男女別に見ると、入所受刑者総数に占める窃盗及び覚醒剤取締法違反の人員の合計の割合は、女性入所受刑者では、平成16年以降、一貫して6割を超えており、特に23年以降、その割合は約8割であるのに対し、男性入所受刑者では、16年以降、一貫して6割未満にとどまっている。また、女性入所受刑者では、16年から23年まで覚醒剤取締法違反の人員が最も多かったものの、24年以降、窃盗の人員が覚醒剤取締法違反の人員を上回っており、女性入所受刑者総数のうち窃盗が4~5割、覚醒剤取締法違反が2~4割程度を占めている。他方、男性入所受刑者では、16年以降、一貫して窃盗の人員が覚醒剤取締法違反の人員を上回っている。
入所受刑者の入所度数別構成比について見ると、女性入所受刑者では、「1度」の構成比は、平成16年以降低下しているものの、27年以降、50~53%台で推移しており、令和5年は52.0%と、なお全体の半分以上を占めており、男性入所受刑者(44.2%)よりも高い。他方、「4~5度」、「6~9度」及び「10度以上」は、いずれも男性入所受刑者よりも低く、女性入所受刑者は、男性入所受刑者よりも入所回数の少ない者が多いといえる。
入所受刑者(懲役)の刑期別構成比について見ると、女性入所受刑者では、令和5年は、「1年以下」の構成比が27.3%、「2年以下」の構成比が37.9%であった。女性入所受刑者の「1年以下」の構成比は、平成26年以降、「2年以下」の構成比は、16年以降、一貫して男性入所受刑者よりも高い。女性入所受刑者は、令和5年の「1年以下」及び「2年以下」の構成比の合計が全体の6割以上を占めているのに対し、男性入所受刑者は6割を下回っている。他方、女性入所受刑者の「5年以下」及び「5年を超える」は、総じて男性入所受刑者よりも低い傾向にあり、女性入所受刑者は、男性入所受刑者よりも刑期の短い者が多いといえる。
出所受刑者(仮釈放又は満期釈放等により刑事施設を出所した者に限る。)の仮釈放率の推移(最近20年間)について見ると、女性出所受刑者は、平成16年以降、69~79%台で上昇低下を繰り返しながら推移し、令和5年は77.5%(前年比3.5pt 上昇)であった。他方、男性出所受刑者は、平成16年以降、21年までは低下していたが、翌年からは上昇傾向にあり、令和5年は61.3%(前年比0.5pt 上昇)であった。女性出所受刑者の仮釈放率は、平成16年以降、一貫して男性出所受刑者(47~61%台)よりも高い。
以上見てきたとおり、入所受刑者の入所度数別構成比、入所受刑者(懲役)の刑期別構成比及び出所受刑者の仮釈放率の各推移の状況等を踏まえれば、受刑者全体として見ると、女性受刑者は、男性受刑者と比べて、刑期が短い者が多く、比較的早期に社会内処遇等へ移行し社会復帰する傾向が認められる。
第4 特別調査
1 調査対象者
今回の特別調査の対象者は、以下のとおりであり、表1は、本調査における調査対象者の属性等を示したものである。
本調査は、全国22庁(主として男性を収容する施設11庁、主として女性を収容する施設9庁、男女を分隔して収容する施設2庁)の刑事施設において、令和4年7月1日から同年12月31日までの間に、新たに処遇施設として刑執行開始時調査を実施した受刑者を調査対象者とした。
なお、調査を行う施設の選定については、主として女性を収容する施設は全ての施設(医療刑務所、拘置所及び令和4年度から女性の収容を開始した喜連川社会復帰促進センターを除く。)を対象とし、主として男性を収容する施設に関しては、調査対象となる女性受刑者の処遇指標の構成、人員及び地域性を踏まえ、これらとの著しい相違や偏りが生じないよう配慮して全国から11庁を選定し、対象とした。
表1 基本的属性等(男女別)

2 調査内容・方法
本調査に使用した調査票は、法務総合研究所が作成した合計29問から成る自記式の質問紙(「健康と生活に関する意識調査」)であり、質問の内容は、年齢、性別、今回受刑することになった事件の概要、動機・理由等の基本情報のほか、逮捕前の生活状況、生活・行動歴、生活意識・価値観・心理的側面等に関するものであった。なお、刑事施設入所時の罪名等の情報については、別途、把握している統計情報に基づき抽出し、符号化を経た上で使用した。
本調査の調査方法は、調査対象者への質問紙の配布・回収を各施設の職員が行い、刑事施設内の適宜の場所(居室、教室等)において回答を求めた。質問紙には、本調査の協力が任意であり、協力の許諾の有無や回答内容によって不利益を被ることはないことを明示して、調査協力に同意が得られた者について無記名で実施し、その回答結果を分析した。
3 分析対象・方法
本白書の特集では、女性受刑者の逮捕前の生活状況、生活歴、意識等について、主として男性受刑者との比較から、その特徴等を明らかにし、女性犯罪者全般に対するより効果的な指導及び支援を検討するための基礎資料を提供することを試みているところ、戸籍上の性別と自認する性別が一致しない者については、それぞれ個別の事情により、その者の処遇上のニーズや必要とされる配慮が大きく異なるものと考えられることなどから、本調査においては、戸籍上の性別と自認する性別が一致する者908人(女性の刑事施設入所者461人、男性の刑事施設入所者447人)を分析の対象とすることとした。
その上で、今回の特別調査は、女性犯罪者について広く総合的にその特徴を明らかにすることに主眼を置いているところ、これまで見てきたとおり、女性による犯罪の中では薬物事犯及び窃盗事犯の占める割合が高いことから、本調査の結果については、①男女の比較に加えて、女性犯罪者の特徴をつかむための一つの手掛かりとして、②薬物事犯者及び③窃盗事犯者に関する分析結果を見ることとした。
4 男女の比較
(1) 今回受刑することになった事件
今回受刑することになった事件中の薬物犯罪(覚醒剤、大麻、その他の違法薬物や危険ドラッグ等の使用・所持・譲渡等(営利目的を含む。)をいう。以下同じ。)の有無について、男女別に見ると、女性受刑者は、男性受刑者よりも「あり」の構成比が高かった(女性43.7%、男性34.3%)。
また、同事件中の窃盗の有無について、男女別に見ると、女性受刑者は、男性受刑者よりも「あり」の構成比が高かった(女性57.7%、男性43.3%)。
なお、いずれについても、本調査において、調査対象者が自ら答えた結果に基づくものである。
(2) 精神疾患・慢性疾患の有無等
逮捕などで身柄を拘束される直前の1年間において、治療や投薬を受けていた精神疾患の有無を男女別に見ると、精神疾患「あり」の構成比は、女性受刑者は5割を超えていた(53.5%)のに対し、男性受刑者は2割程度(22.6%)であった。なお、質問紙には「精神疾患とは、気分の落ち込みや幻覚・妄想など、心身に様々な影響が出る疾患のことです。」と注意書きを付した上で回答を求めた。
精神疾患「あり」と回答した者について、精神疾患の病名(重複計上による。)を男女別に見ると、女性受刑者は「うつ病・双極性障害(躁うつ病)」(66.8%)の該当率が最も高く、次いで、「不安障害(パニック障害など)」(41.8%)、「依存症(薬物・アルコール・ギャンブルなど)」(27.2%)の順であった。女性受刑者は、男性受刑者よりも、「うつ病・双極性障害(躁うつ病)」、「不安障害(パニック障害など)」、「摂食障害」及び「パーソナリティ障害」の該当率が高かった。
また、前記1年間において、治療や投薬を受けていた慢性疾患の有無を男女別に見ると、慢性疾患「あり」の構成比は、女性受刑者が約4割(38.1%)であったのに対し、男性受刑者は約3割(28.2%)であった。なお、質問紙には、慢性疾患の例として「糖尿病、高血圧、ガンなどの身体の病気」を挙げ、「慢性疾患とは、病気の経過が半年ないし1年以上にわたる疾患のことです。」と注意書きを付した上で回答を求めた。
(3) 就労状況・働いていなかった理由
前記1年間における就労状況を男女別に見るとともに、これを65歳未満と65歳以上の年齢別に見ると、65歳未満では、女性受刑者は「無職」(32.0%)の構成比が最も高く、「失業中」も5.6%であり、男性受刑者よりも、働いていなかった者が多かった(男性受刑者の「無職」13.2%、「失業中」6.2%)。
さらに、「失業中」又は「無職」と回答した65歳未満の者について、働いていなかった理由(重複計上による。)を男女別に見ると、図2のとおりである。女性受刑者は「健康上の理由から」(60.0%)の該当率が最も高く、次いで、「子育てや介護等の家庭の事情から」
図2 働いていなかった理由(男女別)
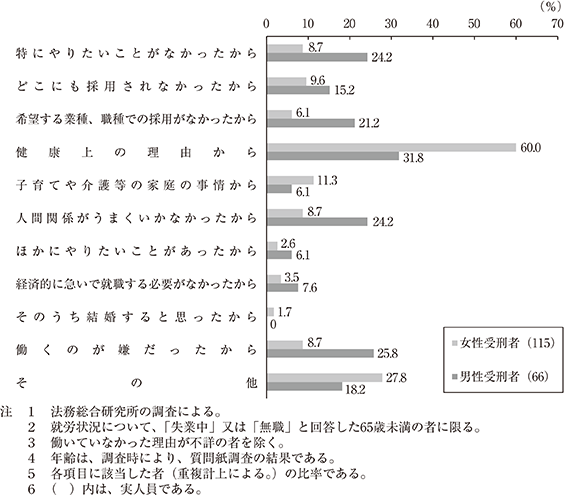
(11.3%)、「どこにも採用されなかったから」(9.6%)の順であった。男性受刑者は「健康上の理由から」(31.8%)の該当率が最も高く、次いで、「働くのが嫌だったから」(25.8%)、「特にやりたいことがなかったから」及び「人間関係がうまくいかなかったから」(各24.2%)の順であった。女性受刑者は、男性受刑者よりも「健康上の理由から」の該当率が高く、男性受刑者は、女性受刑者よりも「特にやりたいことがなかったから」、「希望する業種、職種での採用がなかったから」、「人間関係がうまくいかなかったから」及び「働くのが嫌だったから」の該当率が高かった。
5 薬物事犯者
ここでは、薬物事犯者(今回受刑することになった事件中に薬物犯罪が含まれる者をいう。以下同じ。)の女性に特徴的な傾向を明らかにするため、調査対象となった受刑者の総数の男女別と薬物事犯者の男女別(女性155人、男性126人)の比較を行った。受刑者に対する調査結果のうち、主として生活状況及び交友関係の二つの側面から、薬物事犯者の男女別に特徴的な傾向が見られた項目について取り上げる。
(1) 配偶者・交際相手間の加害・被害経験
配偶者(事実婚、別居中の夫婦及び元配偶者を含む。)や交際相手間での加害経験及び被害経験について、男女別に見ると、総数、薬物事犯者のいずれも、全ての項目で、女性受刑者は、男性受刑者と比べ、「加害・被害なし」の構成比が低く、「加害なし・被害あり」及び「加害・被害あり」の構成比が高かった。また、薬物事犯者の女性受刑者では、総数の場合よりも、全ての項目で「加害・被害なし」の構成比が低く、「加害なし・被害あり」及び「加害・被害あり」の構成比が高かった。特に薬物事犯者の女性受刑者では、身体的暴行の「加害・被害なし」は2割弱にとどまり、心理的攻撃の「加害・被害なし」も3割弱にとどまった。
(2) 小児期逆境体験(ACE)の経験の有無
18歳までの小児期逆境体験(Adverse Childhood Experiences。以下「ACE」という。)の経験の有無(重複計上による。)について、男女別に見ると、総数では、女性受刑者と男性受刑者のいずれも「親が亡くなったり離婚したりした」、「家族から、心が傷つくような言葉を言われるといった精神的な暴力を受けた」、「家族から、殴る蹴るといった体の暴力を受けた」の3項目において、「あり」の該当率が30%を超えた。薬物事犯者の女性受刑者は、前記3項目に加え「母親(義理の母親も含む)が、父親(義理の父親や母親の恋人も含む)から、暴力を受けていた」の「あり」の該当率も30%を超えた。また、薬物事犯者の女性受刑者は、総数の場合及び薬物事犯者の男性受刑者よりも、「あり」の該当率が総じて高い傾向が見られた。
(3) 共犯者との関係
今回受刑することになった事件における共犯者の有無において共犯者がいると回答した受刑者について、事件当時の共犯者との関係(自分から見た共犯者の立場)(重複計上による。)を男女別に見ると、総数、薬物事犯者のいずれも、女性受刑者は「配偶者・交際相手」(総数44.3%、薬物事犯者61.4%)の該当率が最も高く(なお、男性総数6.0%、男性薬物事犯者10.7%)、男性受刑者は「友人・知人」(総数55.0%、薬物事犯者67.9%)の該当率が最も高かった。また、薬物事犯者の女性受刑者では、総数の場合よりも、「配偶者・交際相手」の該当率が更に高かった。
(4) 困りごとの内容
逮捕などで身柄を拘束される直前の1年間において、悩んだり不安に思ったりしていた内容(重複計上による。)について、男女別に見ると、総数、薬物事犯者のいずれも、女性受刑者は「人間関係」(総数55.8%、薬物事犯者71.2%)の該当率が最も高く、男性受刑者は「経済的なこと」(総数60.2%、薬物事犯者52.4%)及び「仕事のこと」(総数55.1%、薬物事犯者53.2%)の該当率が高かった。また、薬物事犯者の女性受刑者では、総数の場合よりも、「人間関係」の該当率が更に高く70%を超えた。
6 窃盗事犯者
調査対象者のうち窃盗事犯者(今回受刑することになった事件中に窃盗が含まれる者をいう。以下同じ。)を年齢層別に見ると、女性は、男性よりも60歳以上の割合が高く、40歳未満の割合が低く、薬物事犯者と比べて年齢層に偏りがあることなどから、ここでは、窃盗事犯者について、男女別に加え、年齢による違いも考慮した上で比較を行うことにより、特に高年齢の女性窃盗事犯者に特徴的な傾向を明らかにする。受刑者に対する調査結果のうち、主として経済的状況及び周囲との関わりの二つの側面から、窃盗事犯者の男女別、年齢別に特徴的な傾向が見られた項目について取り上げる。なお、年齢については、男女別及び年齢別の傾向の違いが明らかであった60歳以上と60歳未満に分けることとする。
(1) 今回受刑することになった窃盗の態様・手口
今回受刑することになった窃盗の態様・手口(重複計上による。)について、男女別及び年齢別に見ると、女性受刑者(60歳以上)は、「万引き」の該当率が95.9%と顕著に高かった。女性受刑者(60歳未満)及び男性受刑者(60歳以上)も、「万引き」の該当率が最も高かったが(それぞれ73.8%、48.3%)、男性受刑者(60歳未満)は、「万引き以外の非侵入窃盗」(42.4%)の該当率が最も高かった。
(2) 事件の動機・理由
今回受刑することになった事件をした動機及び理由(重複計上による。)について、男女別及び年齢別に見ると、いずれの群も、「生活費に困っていたから」の該当率が最も高かったが、男性受刑者(60歳未満)では該当率が60%を上回った(61.2%)ことと比較すると、女性受刑者(60歳以上)の該当率は低く、40%を下回った(37.4%)。女性受刑者(60歳以上)は、「わからない」(21.2%)の該当率が他の群よりも高かった。
(3) 収入源
逮捕などで身柄を拘束される直前の1年間において、生活費をどのように得ていたか(重複計上による。)について、男女別及び年齢別に見ると、女性受刑者(60歳以上)では、「公的年金」(46.9%)の該当率が最も高かった。他方、女性受刑者(60歳未満)及び男性受刑者(60歳未満)では、「自分が働いて得た収入」(それぞれ53.1%、72.2%)の該当率が、また、男性受刑者(60歳以上)では、「生活保護」(56.7%)の該当率がそれぞれ最も高かった。女性受刑者(60歳以上)は、「預貯金」(28.1%)の該当率が他の群よりも高かった。
(4) 一緒に暮らしていた者
前記1年間において、一緒に暮らしていた者(重複計上による。)について、男女別及び年齢別に見ると、女性受刑者(60歳以上)では、「いない(一人暮らし)」(38.7%)の該当率が最も高かった。
(5) 困りごとの内容・相談しなかった理由
前記1年間において、悩んだり不安に思ったりしていた内容(重複計上による。)について、男女別及び年齢別に見ると、女性受刑者(60歳以上)では、「健康上のこと」(51.7%)の該当率が最も高かった。女性受刑者(60歳以上)は、「経済的なこと」、「仕事のこと」、「妊娠や出産のこと」、「人間関係」及び「犯罪行為をしていること」の該当率が他の群よりも低かった。また、女性受刑者(60歳以上)の約1割が「特に悩んだり困ったりしていない」と回答した。
前記「特に悩んだり困ったりしていない」以外の項目を選択した者について、当時、悩みや不安が生じた場合の相談の有無を男女別及び年齢別に見ると、女性受刑者(60歳以上)は、「相談した」の構成比が約5割(49.3%)を占め、他の群よりも高かった。その上で、「相談しなかった」と回答した者について、不安や悩みを相談しなかった理由(重複計上による。)を男女別及び年齢別に見ると、女性受刑者(60歳以上)では、「相談する相手がいなかった」(58.8%)の該当率が最も高かった。女性受刑者(60歳以上)は、「相談してもむだだと思った」(17.6%)の該当率が他の群よりも低かった。
7 女性の抱える困難に応じた処遇・支援の在り方
(1) 心身の健康の回復等に資する処遇・支援の更なる充実
特別調査の結果から、女性受刑者は、男性受刑者と比べて、慢性疾患及び精神疾患により、心身の不安定な健康状態にある者が多く、心身の健康に関する悩みを抱える者も多い上、特に65歳未満の女性受刑者は、心身の不安定な健康状態の影響により自らの力のみでは自立的な生活が困難となる者が多い傾向にあることが明らかとなった。このような状況を踏まえると、女性受刑者の円滑な社会復帰のためには、心身の不安定な健康状態に対する治療等を行い、その回復を図ることはもとより、回復後における心身の健康状態の維持・増進にも資する処遇・支援を充実させていく必要がある。
薬物依存については、現在、刑事施設及び社会内処遇・支援を実施する各機関・団体において、女子依存症回復支援事業や薬物再乱用防止プログラム等の取組が実施されているが、依存症からの回復や治療は刑事施設や保護観察所におけるプログラム等の受講により完結するものではなく、生涯にわたる治療や支援が必要とされることもある。この点、薬物事犯の保護観察対象者については、保護観察終了後も薬物依存からの回復のための必要な支援を受けられるよう、地域における支援体制の構築が図られているところであるが、今後、保護観察対象者以外の者についても、保護観察所が実施する「更生保護に関する地域援助」(以下「地域援助」という。)の取組等により、広く支援体制を構築していくことが期待される。また、女性受刑者は、男性受刑者よりも「うつ病・双極性障害(躁うつ病)」、「不安障害(パニック障害など)」、「摂食障害」及び「パーソナリティ障害」の該当率が高かったことから、これらについても手厚い処遇・支援を行うことが望まれる。摂食障害については、現在、刑事施設において必要な医療体制が整えられており、出所後も保護観察所等における処遇・支援の中で、治療が必要な者に対する個別の指導が行われているところではあるが、女性受刑者は、男性受刑者よりも刑期が短い者が多い傾向にあることからすると、刑事施設を出所した後、保護観察に付されない場合における社会内支援の重要性は高く、このような場合にも、保護観察に付される場合と同程度の、医療機関の継続的な受診につながるような手厚い支援を行うことが望まれる。
(2) 被害経験等による生きづらさを踏まえた処遇・支援の必要性
特別調査の結果から、女性受刑者の中でも薬物事犯者は、被害経験、小児期逆境体験(ACE)、精神疾患等多方面において、問題を抱えている者が多く、それが社会における生きづらさの要因の一つとなっている者もいることがうかがわれた。
現在、少年院では、女子の少年院入院者の多くが虐待等の被害体験や性被害による心的外傷等の精神的な問題を抱えていることを踏まえ、女子少年院在院者の特性に配慮した処遇プログラムが実施されているほか、刑事施設においても、問題を抱える成人女性の特性に配慮した処遇がなされているところ、刑事施設出所後も、受刑に至るまでの生育歴、行動歴を理解した上で、長期的な視点からこれまでの生きづらさに対する治療的、支援的な関わりを行うことが有効であると考えられる。そこで、社会内処遇・支援を実施する保護観察所や更生保護施設においても、同処遇プログラムを実践している女子少年院や刑事施設における処遇のノウハウを活用して処遇・支援に当たることが期待される。また、現在、女性の更生保護施設の一部では、依存症や嗜癖問題について、医療・福祉等の専門家の助言を受けるなどしているところ、このような取組が更に多くの施設で行われ、どの施設においても依存症や嗜癖問題に関する処遇・支援を受けることが可能な状況を作り出すことが望ましい。さらに、薬物事犯者の女性受刑者は、人間関係の悩みなどを持つ者も多く、その生きづらさがより複雑なものとなっている。そのため、このような複雑な状況に対応し、地域の中で継続的な支援が受けられるよう、これまで保護観察所が実施する地域援助の取組等により行われてきた医療・福祉等を行う機関・団体との間での連携等を今後も継続していく必要があるほか、配偶者や親族等に対しても、円滑な社会復帰のための重要な社会資源として更に協力を求める必要がある。もっとも、女性受刑者の中には、配偶者・交際相手からの被害体験等を有している者や、配偶者・交際相手が共犯者である者などもいるため、配偶者・交際相手を更生のための協力者とすべきではない場合もあり、本人の意思を尊重しつつ、適切な環境調整を行うことができるよう慎重に支援等を行う必要がある。
(3) 加齢に伴う不安・悩みや孤立に対する処遇・支援の重要性
特別調査の結果から、女性受刑者のうち特に60歳以上の窃盗事犯者については、加齢に伴い、生活環境や経済状況の変化によって生じる将来への漠然とした不安や、心身の不調の増加に伴い増していく悩みを抱える中で、周囲の人間との関わりが少なくなることによって孤立したまま犯行に至る者が少なくないことがうかがわれた。このような60歳以上の窃盗事犯者の加齢に伴う様々な不安・悩みや孤立に対しては、不安・悩みを解消し、孤立を軽減するための相談先へとつなぐ必要がある。
この点、窃盗事犯者のうち60歳以上の女性受刑者では、相談相手がいないことや、どこに相談すれば良いのか分からないため、悩みごとの相談に至らなかった者が一定程度いたことから、刑事施設のみならず、各支援機関等においても、保護観察所が地域援助の一環として設置している犯罪・非行の地域相談窓口「りすたぽ」等の社会復帰後の相談窓口等に関する広報を更に推進していくことが重要である。また、これまでは、刑事司法手続の終了に伴い、それまで受刑者等に対する処遇・支援等を行ってきた刑事司法関係者との関係も途切れてしまい、その後の相談先を見付けることが難しい場合もあったところ、近年、保護観察所においては、保護観察期間終了後も支援対象者の希望に応じ、精神保健福祉センターその他の関係機関に支援を引き継ぐなどしているほか、支援対象者の家族に対しても、希望に応じ、支援を行っている。そのほかにも、法務省において、更生保護施設退所者等が更生保護施設に通所して支援を受ける「フォローアップ事業」、更生保護施設職員が更生保護施設退所者等の自宅等を訪問するなどして継続的な支援を行う「訪問支援事業」、保護観察所が実施する地域援助、「刑執行終了者等に対する援助」などの新たな取組が実施されていることから、今後もこのような取組のより一層の充実・拡充が期待される。さらに、年齢が高くなるにつれて就労先を見付けることは難しくなる上、そもそも生活に必要な金銭を得る手段が確保されており就労の必要がないケースもあることから、特に高齢の女性犯罪者については、就労支援が必ずしも円滑な社会復帰に結び付くとはいえない場合もある。このように、直ちに福祉的支援を受けるまでには至らず、かつ就労支援も功を奏さない者については、出所後に自らの力で環境を変えることは相当に難しいことから、これらの者に対し、各種地域活動への参加をあっせんするなどして、福祉的支援や就労支援以外の方法でも、社会内での居場所作りを行っていくことが望まれる。
第5 まとめ
本稿では、令和6年版犯罪白書における特集である「女性犯罪者の実態と処遇」の中で、特に、女性を取り巻く近年の社会生活の状況、女性による犯罪の動向等に加え、今回の特別調査の結果を踏まえた分析・検討について紹介するとともに、女性犯罪者に対する処遇・支援の在り方について述べた。
女性受刑者は、男性受刑者とは異なる傾向・特徴があるところ、女性犯罪者の中でも多くの割合を占める薬物事犯者と窃盗事犯者においても、その傾向・特徴はそれぞれ異なっている。したがって、これらを一まとめにせず、個別的な指導・支援を的確に実現する必要がある。本特集では、各種統計資料等に加え、特別調査により、女性犯罪者全体、薬物事犯者及び窃盗事犯者の傾向・特徴を明らかにした。今回の特集が、女性犯罪者の再犯防止及び円滑な社会復帰に向けた取組を進めるための一助となることを期待する。
(法務省法務総合研究所研究部室長研究官)