
トップページ > 刑事政策関係刊行物:犯罪白書 > 最近の犯罪動向と犯罪者の処遇−令和6年版犯罪白書から−
犯罪白書
最近の犯罪動向と犯罪者の処遇 −令和6年版犯罪白書から−
西平 俊秀
はじめに犯罪白書は、犯罪の防止と犯罪者の改善更生を軸として、刑事政策の策定とその実現に資するため、犯罪の動向と犯罪者処遇の実情を分析・報告している。令和6年版犯罪白書も、統計資料等に基づき、第1編から第6編(ルーティーン部分)において、令和5年を中心とする最近の犯罪の動向と犯罪者処遇の実情を概観・分析した。また、第7編の「女性犯罪者の実態と処遇」では、女性を取り巻く社会状況などについて概観するとともに、受刑者を対象として実施した特別調査の結果から、女性受刑者の傾向・特徴を明らかにし、女性犯罪者の再犯防止及び円滑な社会復帰を図るために必要と考えられる今後の処遇や支援の在り方について検討を行った。
このうち、本稿においては、ルーティーン部分について、その要点を紹介する(法令名・用語・略称については、特に断りのない限り本白書で用いられたものを使用するほか、元号については、直前の元号と同様である場合は記載を省略する。)。
1 最近の犯罪動向
(1) 刑法犯
ア 認知件数
令和5年における刑法犯の認知件数は、70万3,351件(前年比10万2,020件(17.0%)増)であった。刑法犯の認知件数は、平成14年に戦後最多の約285万件に達した後、15年以降は減少に転じ、27年から令和3年までは戦後最少を更新していたが、4年は20年ぶりに増加し、5年も引き続き増加した。平成15年からの認知件数の減少は、刑法犯の7割近くを占める窃盗の認知件数が大幅に減少し続けたことに伴うものであり、令和4年からの認知件数の増加は、窃盗の認知件数が大幅に増加し続けたことに伴うものである。窃盗を除く刑法犯の認知件数も、17年から減少し続けていたが、令和5年は21万9,656件(前年比2万6,236件(13.6%)増)であり、特に詐欺、傷害及び暴行の認知件数が顕著に増加した。(図1(白書1-1-1-1図)参照)。
罪名別の構成比では、窃盗(68.8%)が最も高く、次いで、器物損壊(8.1%)、詐欺(6.5%)、暴行(4.3%)の順であった。
イ 検挙人員と検挙率
令和5年における刑法犯検挙人員は、18万3,269人(前年比1万3,860人(8.2%)増)であった。刑法犯検挙人員は、平成16年(約39万人)をピークに減少し続けていたが、令和5年は前年と比べて増加した。罪名別の構成比では、窃盗(46.7%)が最も高く、次いで
図1 刑法犯 認知件数・検挙人員・検挙率の推移
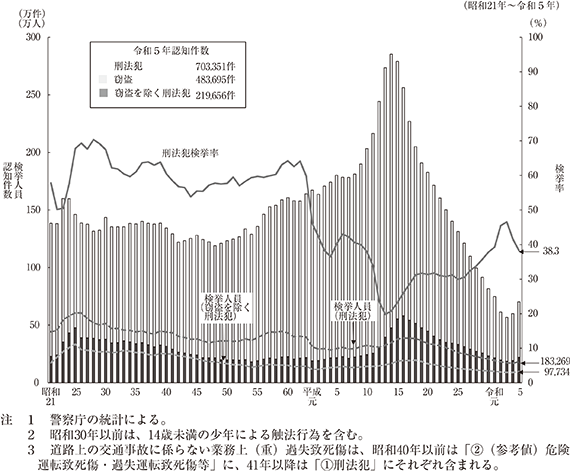
暴行(13.8%)、傷害(10.9%)、横領(5.5%)の順であった。
令和5年における刑法犯の検挙率は、38.3%(前年比3.3pt 低下)であった。刑法犯の検挙率は、平成13年に戦後最低(19.8%)を記録したが、14年から回復傾向にあり、一時横ばいで推移した後、26年以降上昇していたものの、令和4年に低下に転じ、5年も引き続き低下した。
ウ 主要な犯罪の動向
(ア) 窃盗
窃盗の認知件数は、戦後最多を記録した平成14年をピークに15年から減少に転じ、26年以降令和3年まで、毎年戦後最少を更新し続けていたが、5年は48万3,695件(前年比7万5,784件(18.6%)増)であった。検挙率は、平成26年から令和3年まで上昇し続けていたが、4年から2年連続で低下し、5年は32.5%(同3.8pt低下)であった。手口別に構成比を見ると、認知件数では自転車盗(33.9%)が最も高く、検挙件数では万引き(39.9%)が最も高い。なお、特殊詐欺に関係する手口のうち、払出盗の認知件数は、5年は8,263件(同2.4%増)と前年から増加したのに対し、職権盗の認知件数は、5年は1,578件(同31.3%減)と大きく減少した。
(イ) 殺人
殺人の認知件数は、平成16年から28年までは減少傾向にあり、その後はおおむね横ばいで推移し、令和3年から2年連続で戦後最少を更新したが、5年は増加し、912件(前年比59件(6.9%)増)であった。検挙率は、安定して高い水準(5年は95.6%)にある。
(ウ) 強盗
強盗の認知件数は、平成16年から減少傾向にあり、令和3年には戦後最少を更新したものの、翌年から2年連続で増加し、5年は1,361件(前年比213件(18.6%)増)であった。検挙率は、平成17年から上昇傾向にあり、令和5年は90.5%(同1.8pt 低下)と2年連続で低下したものの、依然として高い水準にある。
(エ) 不同意性交等・不同意わいせつ
不同意性交等(刑法の一部を改正する法律(平成29年法律第72号)による改正前は強姦(準強姦を含む。)をいい、同改正後、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和5年法律第66号)による改正前は強制性交等(準強制性交等を含む。)、前記強姦及び監護者性交等をいい、同改正後は不同意性交等、前記強制性交等、前記強姦及び監護者性交等をいう。)の令和5年における認知件数は2,711件(前年比1,056件(63.8%)増)であり、検挙件数は2,073件(同672件(48.0%)増)であった。検挙率は、平成27年以降令和3年まで、いずれの年も90%台と高水準で推移していたが、5年は前年に引き続き低下し、76.5%(同8.2pt低下)であった。
不同意わいせつ(前記平成29年法律第72号による改正前は強制わいせつ(準強制わいせつを含む。)をいい、同改正後、前記令和5年法律第66号による改正前は前記強制わいせつ及び監護者わいせつをいい、同改正後は不同意わいせつ、前記強制わいせつ及び監護者わいせつをいう。)の令和5年における認知件数は6,096件(前年比1,388件(29.5%)増)であり、検挙件数は4,813件(同751件(18.5%)増)であった。検挙率は、平成15年以降上昇傾向にあったところ、令和5年は79.0%(同7.3pt低下)であった。
(オ) 傷害・暴行・脅迫
傷害の認知件数は、平成16年から減少傾向にあったが、令和4年から2年連続で増加し、5年は2万2,169件(前年比2,655件(13.6%)増)であった。暴行の認知件数は、平成18年以降おおむね高止まりの状況にあった後、令和元年から減少傾向にあったが、5年は4年に続き増加し、3万196件(同2,347件(8.4%)増)であった。脅迫の認知件数は、平成24年に大きく増加し、同年以降は3,000件台で推移していたが、令和4年は4,000件を上回り、5年は4,535件(同498件(12.3%)増)であった。いずれの検挙率も、平成16年前後からおおむね上昇傾向にある。
(カ) 詐欺
詐欺の認知件数は、平成24年から増加傾向を示し、その後、30年から減少したが、令和3年から再び増加しており、5年は4万6,011件(前年比8,083件(21.3%)増)であった。検挙率は、平成27年以降は上昇傾向にあったが、令和3年から低下しており、5年は36.2%(同6.2pt 低下)であった。特殊詐欺(被害者に電話をかけるなどして対面することなく信頼させ、指定した預貯金口座への振込みその他の方法により、不特定多数の者から現金等をだまし取る犯罪の総称。現金等を脅し取る恐喝及びキャッシュカード詐欺盗(警察官や銀行協会、大手百貨店等の職員を装って被害者に電話をかけ、「キャッシュカードが不正に利用されている」等の名目により、キャッシュカード等を準備させた上で、隙を見るなどし、同キャッシュカード等を窃取するもの)を含む。)の認知件数は、同じく平成23年から増加傾向を示し、その後、30年から再び減少したが、令和3年から増加しており、5年は1万9,038件(同8.4%)増)であった。検挙率は、同じく平成27年以降は上昇傾向にあったが、令和3年から低下しており、5年は37.9%(同0.1pt上昇)であった。
(2) 特別法犯
令和5年における特別法犯の検察庁新規受理人員は、29万7,507人(前年比7.8%増)であった。このうち、道路交通法違反が21万2,310人であり、特別法犯全体の71.4%を占める。
道交違反(道路交通法違反及び保管場所法違反をいう。)を除く特別法犯の検察庁新規受理人員は、平成19年(11万9,813人)をピークに減少傾向にあったが、令和5年は8万4,331人(前年比5.1%増)であった。罪名別に構成比を見ると、覚醒剤取締法(11.5%)、大麻取締法(11.1%)、軽犯罪法(8.7%)、入管法(8.0%)、廃棄物処理法(7.6%)、銃刀法(6.2%)の各違反の順であった。
2 犯罪者の処遇
(1) 検察
令和5年における検察庁新規受理人員の総数は、78万6,707人(前年比6.2%増)であった。罪種別の構成比を見ると、過失運転致死傷等及び道交違反がその6割強を占めている。5年における検察庁終局処理人員は79万1,457人(同6.2%増)であり、その内訳は、公判請求7万5,384人、略式命令請求16万2,761人、起訴猶予44万4,261人、その他の不起訴6万2,960人、家庭裁判所送致4万6,091人であった。公判請求率は、平成14年から26年までは7%台で推移した後、同年以降上昇傾向にあり、令和5年は10.1%(同0.3pt 上昇)であった。
(2) 裁判
裁判確定人員は、平成12年(98万6,914人)から毎年減少していたところ、令和5年は20万1,990人(前年比0.7%増)であり、最近10年間で40.2%減少している。有期懲役判決が確定した人員(3万9,220人)について、全部執行猶予率(有期懲役人員に占める全部執行猶予人員の比率)は63.2%であった。また、無罪確定者は、79人(裁判確定人員総数の0.04%)であった。
令和5年の裁判員裁判対象事件の第一審における判決人員は、807人であり、そのうち、死刑が1人、無期懲役が10人、無罪が12人であった。また、有期懲役のうち、152人が全部執行猶予(うち79人が保護観察付)であった。
(3) 矯正
入所受刑者の人員は、平成19年から減少し続け、令和5年は1万4,085人(前年比2.6%減)と戦後最少を更新した。5年末現在の刑事施設における被収容者の収容人員は、4万178人(前年末比3.3%減)であり、収容率(既決)は51.0%(同2.2pt 低下)であった。
令和5年の入所受刑者の罪名別構成比では、男女共に、窃盗が最も高く(男性36.6%・女性55.4%)、次いで、覚醒剤取締法違反(男性18.1%・女性24.2%)、詐欺(男性10.1%・女性6.7%)の順であった。入所受刑者の年齢層別構成比を見ると、女性は、男性と比べて高齢者の構成比が高かった(男性13.3%・女性22.7%)。
令和5年における出所受刑者(1万6,986人)について、満期釈放又は一部執行猶予の実刑部分終了により出所した者の比率は、 37.0%(前年比0.9pt 低下)であった。
(4) 更生保護
令和5年の保護観察開始人員は、仮釈放者(全部実刑者)9,468人(前年比1.7%減)、仮釈放者(一部執行猶予者)743人(同25.8%減)、保護観察付全部執行猶予者1,682人(同1.3%増)、保護観察付一部執行猶予者935人(同24.2%減)であった(いずれも事件単位の延べ人員)。
保護観察付全部執行猶予者の保護観察開始人員は、刑の一部執行猶予制度が開始された平成28年以降を見ると減少し続けており、令和5年の全部執行猶予者の保護観察率は6.1%(前年比0.1pt 低下)であった。
3 少年非行の動向と非行少年の処遇
少年による刑法犯検挙人員(触法少年の補導人員を含む。)は、平成16年以降減少し続けていたが、令和4年から増加に転じ、5年は2万6,206人(前年比25.3%増)であった。少年人口比(10歳以上の少年人口10万人当たりの刑法犯検挙人員)も、5年は前年に引き続き上昇し、244.0(同50.7pt 上昇)であったが、全体としては低下傾向が見られる。特定少年(罪を犯した18・19歳の者をいう。)の少年による刑法犯検挙人員に占める割合は、3年以降低下しており、5年は20.7%であった。少年による刑法犯検挙人員の罪名別構成比では、窃盗(53.1%)が最も高く、次いで、傷害(9.7%)、暴行及び横領(いずれも6.4%)であった。
道交違反に係るもの以外の少年保護事件の家庭裁判所新規受理人員は、平成16年以降、毎年減少し続けていたが、令和5年は4万253人(前年比18.9%増)に増加した。犯行時16歳以上の少年による故意の犯罪行為で被害者を死亡させた罪の事件、及び、特定少年に係る事件のうち、死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件(ただし、故意致死に該当する事件を除く。)であって、その罪を犯すとき特定少年に係るものについては、家庭裁判所は、原則として検察官に送致しなければならないが、これに該当する原則逆送事件の終局処理人員(年齢超過による検察官送致を除く。)の推移(原則逆送制度が開始された平成13年以降)は、14年(83人)のピーク後は、減少傾向にあったが、原則逆送事件の対象が拡大した令和4年から増加に転じており、5年は総数が160人(前年比102人増)であり、検察官送致(刑事処分相当)65人(同33人増)、保護処分85人(同61人増)と、いずれも大幅に増加した。令和5年における原則逆送事件の家庭裁判所終局処理人員を処理区分別及び特定少年・特定少年以外の少年の別に見ると、特定少年は、検察官送致(刑事処分相当)65人、保護処分83人、その他10人であったのに対し、特定少年以外の少年は、保護処分2人であった。
少年鑑別所入所者の人員は、平成16年から減少し続けていたが、令和4年から2年連続で増加し、5年は5,451人(前年比17.0%増)であった。
少年院入院者の人員は、最近30年間では、平成12年(6,052人)をピークに減少傾向が続いており、令和元年からは、昭和24年以降最少を更新し続けていたが、令和5年は1,632人(前年比22.5%増)であった。また、同年の女子比は、8.2%(同1.5pt 低下)であった。保護観察処分少年(家庭裁判所の決定により保護観察に付されている者)の保護観察開始人員は、平成11年以降減少し続けていたが、令和5年は前年と比べて増加し、10,081人(前年比10.7%増)であった。少年院仮退院者の保護観察開始人員は、平成15年以降減少傾向にあり、令和5年は1,327人(同2.4%減)であった。また、特定少年について見ると、同年は、保護観察処分少年5,806人(うち更生指導1,506人)、少年院仮退院者519人であった。
4 各種犯罪の動向と各種犯罪者の処遇
(1) 交通犯罪
交通事故の発生件数及び負傷者数は、平成17年以降減少傾向にあり、令和5年はそれぞれ30万7,930件(前年比2.4%増)、36万5,595人(同2.5%増)であった。死亡者数も、平成4年(1万1,452人)をピークに減少傾向にあったが、令和5年は前年より増加し、2,678人(同68人増)であった。
令和5年における危険運転致死傷の検挙人員は、778人(前年比5.6%増)であり、うち致死事件は33人(同16人減)であった。
令和5年における道交違反の取締件数は、453万1,869件(前年比10.8%減)であった。そのうち、送致事件(非反則事件として送致される事件)の取締件数は、平成12年から減少し続けていたが、令和5年は21万7,353件(同11.7%増)であった。5年の送致事件の構成比を違反態様別に見ると、速度超過(26.4%)、酒気帯び・酒酔い(9.9%)、無免許(8.1%)の順であった。酒気帯び・酒酔いの取締件数は、平成12年以降減少傾向にあるところ、令和5年は2万1,467件(同8.3%増)であり、平成期最多であった平成9年(34万3,593件)の約16分の1の水準であった。なお、令和5年における妨害運転(妨害運転により著しい交通の危険を生じさせた場合の加重処罰規定を含む。)の取締件数は、102件であった。
(2) 薬物犯罪
覚醒剤取締法違反(覚醒剤に係る麻薬特例法違反を含む。)の検挙人員は、平成13年から減少傾向にあり、令和5年は6,073人(前年比3.4%減)で、5年連続で1万人を下回った。なお、令和5年における覚醒剤の押収量は、1,601.6kg で前年(475.3kg)の約3.4倍であった。
大麻取締法違反(大麻に係る麻薬特例法違反を含む。)の検挙人員は、平成6年(2,103人)と21年(3,087人)をピークとする波が見られた後、26年から8年連続で増加し、29年から令和3年までは、昭和46年以降における最多を記録し続け、令和4年はやや減少したものの、5年は再び増加し、6,703人(前年比20.9%増)であった(図2(白書4 - 2 - 1 - 4図)参照)。このうち、20歳代の検挙人員は、平成26年から増加し続けており、令和5年は3,545人(同24.3%増)で、大麻取締法違反による検挙人員の過半数を占めた(54.7%)。少年による大麻取締法違反の検挙人員も、平成26年以降増加傾向にあり、5年は1,222人(同34.0%増)であった。
図2 大麻取締法違反等 検挙人員の推移(罪名別)
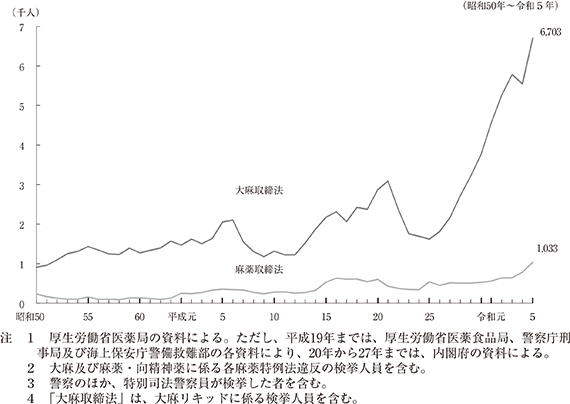
(3) 暴力団犯罪
暴力団構成員等(暴力団構成員及び準構成員その他の周辺者)の刑法犯検挙人員は、減少傾向にあり、令和5年は6,068人、刑法犯検挙人員に占める暴力団構成員等の比率は3.3%であった。罪名別では、詐欺(1,332人)、傷害(1,186人)、窃盗(889人)、暴行(527人)、恐喝(460人)の順に多く、全検挙人員に占める暴力団構成員等の比率は、賭博(36.0%)、恐喝(33.7%)、逮捕監禁(29.9%)、強盗(14.8%)の順で高かった。
暴力団構成員等の特別法犯検挙人員も、減少傾向にあり、令和5年は3,542人、特別法犯検挙人員に占める暴力団構成員等の比率は6.2%であった。罪名別では、覚醒剤取締法(1,912人)、大麻取締法(705人)、風営適正化法(105人)、麻薬取締法(102人)、銃刀法(80人)の各違反の順で多く、全検挙人員に占める暴力団構成員等の比率を見ると、暴力団排除条例違反(100.0%)、暴力団対策法違反(83.3%)の順で高かった。
(4) 財政経済犯罪
税法違反のうち、消費税法違反の検察庁新規受理人員は、金の密輸入事件の増加の影響もあり、平成28年から30年にかけて急増した後、令和元年から減少に転じ、4年は再び増加したが、5年は減少し、69人(前年比5.5%減)であった。金融商品取引法違反の検察庁新規受理人員は、平成28年以降、令和2年(37人)を除いて50人前後で推移していたが、5年は72人であった。5年度における証券取引等監視委員会による同法違反の告発は、4件・11人(法人を含む。)であった。
(5) サイバー犯罪
不正アクセス行為(不正アクセス禁止法11条に規定する罪)の認知件数は、同法が施行された平成12年以降、増減を繰り返しながら推移し、令和5年は6,312件(前年比186.9%増)であった。また、不正アクセス行為後の行為の内訳を構成比で見ると、「インターネットバンキングでの不正送金等」(88.7%)が最も高く、次いで、「メールの盗み見等の情報の不正入手」(3.2%)、「インターネットショッピングでの不正購入」(1.5%)の順であった。
サイバー犯罪のうち、インターネットを利用した詐欺や児童買春・児童ポルノ禁止法違反等、高度情報通信ネットワークを不可欠な手段として利用した犯罪の検挙件数は、平成29年から増加傾向にあり、令和5年は1万958件(前年比0.5%増)であった。罪名別に見ると、前年と比べ、犯罪収益移転防止法違反は86.5%、ストーカー規制法違反は27.7%、名誉毀損は26.2%、脅迫は12.2%増加した。一方、わいせつ物頒布等は27.2%、青少年保護育成条例違反は14.7%、詐欺は13.6%、児童買春・児童ポルノ禁止法違反は9.4%減少した。
(6) 児童虐待・配偶者からの暴力・ストーカー等に係る犯罪
児童虐待に係る事件(刑法犯等として検挙された事件のうち、児童虐待防止法2条に規定する児童虐待が認められたもの)の検挙件数・検挙人員は、平成26年以降大きく増加し、令和5年は2,385件(前年比9.4%増)・2,419人(同8.9%増)であり、それぞれ直近から20年前の平成16年(284件、311人)と比べると約8.4倍、約7.8倍であった(図3(白書4-6-1-1)参照)。
図3 児童虐待に係る事件 検挙件数・検挙人員の推移(罪名別)
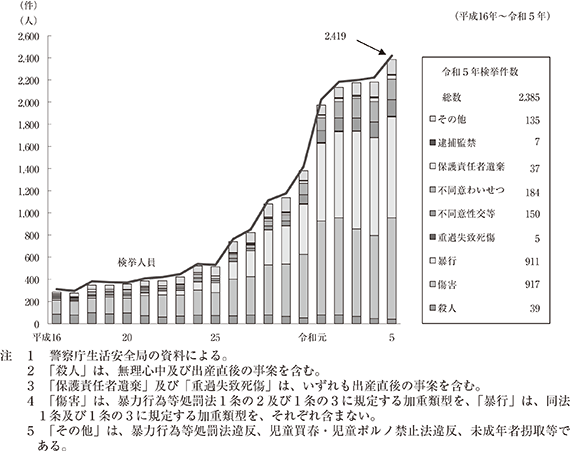
配偶者からの暴力事案等の検挙件数について見ると、配偶者暴力防止法に係る保護命令違反の検挙件数は、平成27年以降減少傾向にあり、令和5年は49件(前年比3件増)であった。その一方、刑法等の他法令による検挙件数の総数は、平成23年以降増加しており、令和2年から3年連続減少したものの、5年は8,636件(同101件増)であり、顕著に増加し始めた平成22年と比較すると約3.7倍であった。特に、暴行及び傷害の検挙件数が大きく増加している。
ストーカー規制法による警告の件数は、平成29年から減少傾向にあり、令和5年は1,534件(前年比17.9%減)であった。同法による禁止命令等の件数は、平成29年から急増し、令和5年は1,963件(同12.6%増。うち緊急禁止命令等は1,179件)であった。ストーカー規制法違反の検挙件数は、平成24年から著しく増加し、30年から令和4年までは増減を繰り返していたが、5年は1,081件(同5.2%増。著しく増加した平成24年の前年である23年の約5.3倍)、刑法犯及び特別法犯(ストーカー規制法を除く。)による検挙件数は1,708件(同3.5%増。同約2.2倍)であった。なお、令和5年におけるストーカー事案に関する相談等件数(ストーカー規制法その他の刑罰法令に抵触しないものも含む。)は、1万9,843件(同3.7%増)であった。
(7) 女性による犯罪・非行
女性の刑法犯検挙人員は、平成17年に戦後最多(8万4,162人)を記録した後、18年から減少傾向にあるところ、令和5年は3万9,370人(前年比6.3%増)であった。検挙人員の女性比は、近年20〜22%で推移しており、5年は21.5%であった。同年における女性の刑法犯検挙人員を罪名別構成比で見ると、窃盗が約7割を占め(万引き51.4%・万引き以外の窃盗16.5%)、男性の罪名別構成比(同20.3 %・同20.6 %)と比べて顕著に高く、次いで、傷害・暴行(15.0%。男性の罪名別構成比27.3%)であった。
女性入所受刑者の人員は、平成19年に若干減少した後はおおむね横ばいで推移した後、28年から減少傾向にあり、令和5年は1,486人(前年比4.4%減)であった。最近20年間の入所受刑者の女性比は、平成27年まで上昇し続け、28年から横ばいとなっていたが、令和2年(10.6%)に再び上昇して以降、10%台が続いており、5年は10.6%であった。女性の入所受刑者を罪名別で見ると、平成24年以降は、窃盗が覚醒剤取締法違反を上回っており、令和5年は823人であった。
女子の少年院入院者の人員は、平成18年から減少傾向にあるところ、令和5年は134人(前年比3.9%増)であり、少年院入院者の女子比は、8.2%であった。非行名別に見ると、窃盗(25人)、詐欺(23人)、覚醒剤取締法違反、傷害・暴行及びぐ犯(いずれも13人)の順に多かった。
(8) 高齢者による犯罪
高齢者の刑法犯検挙人員は、平成20年(4万8,786人)をピークとして高止まりの状況が続いた後、28年から令和4年まで減少し続けたが、5年は4万1,099人(前年比5.0%増)であった。高齢者率は、平成10年以降、他の年齢層の検挙人員の減少傾向が高齢者層と比べて大きかったことから上昇傾向にあったが、令和5年は高齢者だけでなく他の年齢層の検挙人員も増加(同9.1%増)したことから低下し、22.4%(同0.7pt 低下)であった。女性の高齢者率は、平成10年から29年(34.3%)まで上昇し続けた後は横ばいで推移し、令和5年は32.5%(同0.7pt 低下)であった。
令和5年における高齢者の刑法犯検挙人員の罪名別構成比を見ると、窃盗が高く(万引き49.2%・万引き以外の窃盗19.0%。全年齢層では同27.0%・同19.7%)、特に、女性高齢者は、約9割が窃盗(同71.4%・同16.4%)であり、そのうち万引きによるものの構成比が約8割と顕著に高い。
(9) 外国人による犯罪
来日外国人による刑法犯の検挙件数は、平成17年(3万3,037件)のピーク後に減少し続け、29年に一旦増加に転じたものの、30年から再び減少傾向にあったが、令和5年は前年より1,492件増加し、1万40件(前年比17.5%増)であった。その罪名別構成比を見ると、窃盗(61.2%)、傷害・暴行(12.5%)、詐欺(6.4%)の順に高かった。
来日外国人による特別法犯の検挙件数は、平成16年をピークに24年まで減少した後、25年からの増減を経て、28年から5年連続で増加し、令和3年から2年連続で減少したものの、5年は8,048件(前年比31.6%増)であった。このうち、主な罪名・罪種を見ると、入管法違反(5,782件)、薬物関係法令違反(覚醒剤取締法、大麻取締法、麻薬取締法、あへん法及び麻薬特例法の各違反。1,083件)、風営適正化法違反(51件)、売春防止法違反(7件)であった。
令和5年における来日外国人被疑事件(過失運転致死傷等及び道交違反を除く。)の検察庁新規受理人員(1万7,463人)の地域・国籍別構成比を見ると、ベトナム(37.9%)、中国(18.9%)、ブラジル(5.3%)の順に高かった。
(10) 精神障害のある者による犯罪等
令和5年における精神障害者等(精神障害者及び精神障害の疑いのある者)の刑法犯検挙人員は、1,286人(精神障害者1,021人、精神障害の疑いのある者265人)であり、罪名別では、傷害・暴行(422人)が最も多く、次いで、窃盗(232人)であった。また、同年における刑法犯検挙人員の総数に占める精神障害者等の比率は、0.7%であり、罪名別では、放火(11.3%)、殺人(5.9%)の順に高かった。
5 再犯・再非行
令和5年に刑法犯により検挙された者のうち、再犯者(前に道路交通法違反を除く犯罪により検挙されたことがあり、再び検挙された者)の人員は8万6,099人、初犯者の人員は9万7,170人であった。
刑法犯検挙人員のうち、再犯者の人員は、平成18年(14万9,164人)をピークとして漸減状態にあったが、令和5年は前年より6.1%増加した。他方、初犯者の人員は、平成16年(25万30人)をピークとして、その後は減少し続けていたが、令和5年は前年より10.1%増加した。再犯者の人員が減少に転じた後も、それを上回るペースで初犯者の人員が減少し続けたこともあり、再犯者率(刑法犯の検挙人員に占める再犯者の人員の比率)は平成9年以降上昇傾向にあったが、令和3年から3年連続で低下し、5年は47.0%(前年比0.9pt 低下)であった(図4(白書5-1-1図)参照)。
図4 刑法犯 検挙人員中の再犯者人員・再犯者率の推移
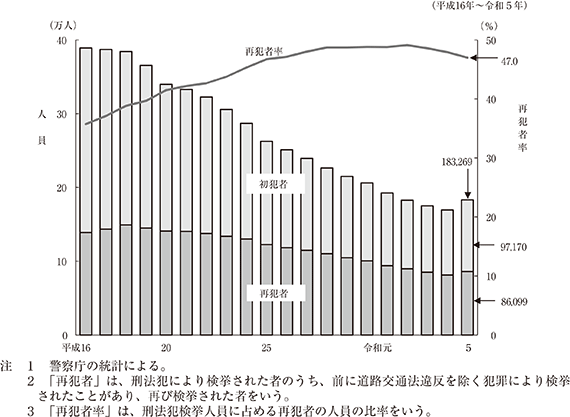
刑法犯により検挙された20歳以上の者のうち、有前科者(道路交通法違反を除く犯罪の前科を有する者)の人員は、平成18年をピークに令和4年まで減少し続け、5年は4万4,312人(前年比5.4%増)と増加したものの、20歳以上の刑法犯の検挙人員総数が同様に増減していることもあり、有前科者率(刑法犯の20歳以上の検挙人員に占める有前科者の人員の比率)は、平成9年以降27〜29%台でほぼ一定しており、令和5年は27.0%であった。罪名別では、刑法犯全体(27.0%)と比べ、恐喝(52.4%)、強盗(41.5%)、詐欺(33.3%)の有前科者率が特に高い。
令和5年に起訴された者(過失運転致死傷等及び道交違反を除く。)の犯行時の身上を見ると、全部執行猶予中の者が5,647人(うち751人が保護観察中)、一部執行猶予中の者が404人(うち394人が保護観察中)、仮釈放中の者が545人、保釈中の者が145人であった。
令和5年の入所受刑者人員総数(1万4,085人)のうち、再入者の人員は7,748人(前年比5.3%減)であり、再入者率は55.0%(同1.6pt低下)であった。うち女性の再入者は714人(同4.5%減)であり、再入者率は男性と比べると低い48.0%であった。
出所受刑者の再入所状況については、令和元年の出所受刑者の5年以内再入率(ある年の出所受刑者人員のうち、出所後の犯罪により、出所年を1年目として5年目(令和元年の出所受刑者であれば令和5年)の年末までに再入所した者の人員の比率)(総数)を見ると34.1%であり、平成26年の出所受刑者の10年以内再入率(総数)を見ると44.9%であった(図5(白書5 - 3 - 6図)参照)。
令和元年の出所受刑者の5年以内再入率を罪名別に見ると、窃盗(42.7%)が他の罪名と比べて高く、覚醒剤取締法違反(38.9%)、傷害・暴行(32.1%)、及び詐欺(20.5%)がそれに続いた。また、平成12年から令和元年までの間の各年における出所受刑者の5年以内再入率を出所事由別に見ると、いずれの年も満期釈放者(平成28年以降の出所受刑者については一部執行猶予の実刑部分の刑期終了により刑事施設を出所した者を含む。)は仮釈放者よりも再入率が高かった。
なお、出所受刑者の2年以内再入率(総数)は、低下傾向が続いており、令和4年は13.0%であった。
図5 出所受刑者の出所事由別再入率
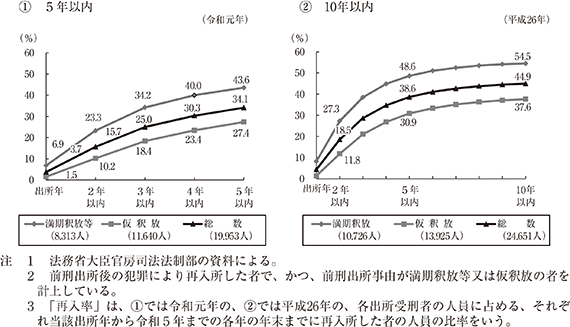
再非行少年率(少年の刑法犯検挙人員に占める再非行少年(前に道路交通法違反を除く非行により検挙(補導)されたことがあり、再び検挙された少年)の人員の比率)は、平成10年から28年まで上昇し続けた後、29年以降は低下傾向にあり、令和5年は30.2%(前年比1.5pt低下)であった。令和元年の少年院出院者について、5年以内再入院率は14.2%、再入院・刑事施設入所率は21.2%であり、令和4年の少年院出院者について、2年以内再入院率は9.1%、再入院・刑事施設入所率は10.1%であった。
6 統計上の犯罪被害
人(法人その他の団体を除く。)が被害者となった刑法犯の認知件数及び男女別の被害発生率(人口10万人当たりの認知件数)は、平成14年のピーク後に減少・低下し続けていたが、令和4年から2年連続して増加・上昇し、5年は、認知件数が53万5,999件、被害発生率が男性580.1・女性289.8であり、元年の約9割の水準にまで達した。
令和5年において、生命・身体に被害をもたらした刑法犯の死傷者総数は、2万6,149人(うち死亡者608人、重傷者(全治1か月以上)2,829人)であり、死傷者総数は直近から20年前の平成16年と比べて約2分の1、死亡者数は同じく16年と比べて2分の1以下であった。
令和5年において、財産犯(強盗、窃盗、詐欺、恐喝、横領及び遺失物等横領。被害者が法人その他の団体である場合を含む。)による被害総額は、約2,519億円(うち現金被害額約1,804億円)であり、財産犯による被害総額を罪名別に見ると、詐欺によるもの(被害総額の64.5%)、窃盗によるもの(同28.8%)の順に多かった。このうち、現金被害額は、詐欺によるものが最も多く、財産犯による現金被害総額の8割以上を占めた。なお、同年の特殊詐欺事件全体の被害総額は、約453億円であり、前年に引き続き増加した。
(法務省法務総合研究所研究部室長研究官)