
�g�b�v�y�[�W �� �Y������W���s���F�ƍߔ��� �� �����ƍߎ҂̐����Â炳��j�[�Y�ɑΉ����邽�߂�
�ƍߔ���
�����ƍߎ҂̐����Â炳��j�[�Y�ɑΉ����邽�߂�
�n糁@�a��
�͂��߂��@���҂�̌����O���[�v�����g�ށu�����̍ĔƖh�~��ړI�Ƃ����i�@�ƕ����̃V�[�����X�ȘA�g�V�X�e���Ɋւ��錤���i��\�F�{���v�h�j�v1�i�ȉ��u�{�����v�Ƃ����j�ł́A�����̎Љ�A�Ɍ��������@�֘A�g�̂�����ɂ��Č������邽�߁A2022�N����2024�N�ɂ����đS���̏����Y���{�݂⏗���o���҂������X���ی�{�݁A�����ɑ���x�������NPO �@�l�⎩���O���[�v�A�s���@�ււ̖K�⒲�����s�����B�{�����́A���̂悤�Ȗ��ӎ�����J�n���ꂽ���̂ł���B�u���݁A�ĔƖh�~���i�v��ɉ����Ďi�@�ƕ������ˋ������g�Ȃǂ��i�߂��Ă��邪�A����܂ő������߂�j����Y�҂̉ۑ�ɏœ_�Ă������E�����Ƃ̘A�g�ɏd�_���u����A�����̐����Â炳��j�[�Y�ւ̑Ή����\���ɂȂ���Ă��Ȃ������B�����̍ĔƖh�~�̂��߂ɂ́A�������L�̕ی�v����ƈ����j�[�Y����肵�A�Ƒ��Ȃǂ̐l�ԊW�̒�����x�����d�_�I�ɐ}��A�Y���{�ݒi�K����A�o����̒n�搶���蒅�Ɋւ��x���������E���p���A�A�J�x���ɂƂǂ܂�Ȃ���I�ȃP�A�T�[�r�X�̗��p����������K�v������B�v
�@���҂�̖{�����O���[�v�́A�Y���{�݂̂����A�S����12�{�݂��鏗���Y���{�݂̑S�ċy�ѓ����{���l������ÃZ���^�[�̖K�⒲�����s����2�B�܂��A�����o���҂������X���ی�{�݂͑S���q�{�݂V�{�y�ђj���{�݂W�̂����R�{�݂�K�₵��3�B�܂��A�Љ���ŏo���҂����p�ł��鎑���Ƃ��āANPO �@�l���J�o���[�i�k�C���j�A�_���N�A���茧�n�搶���蒅�x���Z���^�[�A���ꌧ���_�ی������Z���^�[�Ȃǂ�K�₵���B�܂��A�����W�F���_�[���L�̖��ł��邩�ɂ��ċc�_���s�����߂ɁA�������̒j���Y���{�݂�A���Q���X���ی��Y�S���A�x�R�{�����A�x�R�_���N�Ȃǂ̒j���o���҂������{�݂�K�₵�A�c�_���s����4�B
�@�{�e�ł́A�ߘa�U�N�Ŕƍߔ����Ɏ����ꂽ�����ƍߎ҂̎��ԂɊւ��铝�v�╶�����T�ς��A�M�҂�ɂ��{�����̒��ōs���������Y���{�݂ւ̖K�⒲���ɂ���Č��o���ꂽ�ۑ�̂����A�W�F���_�[�ɔz�����邱�ƂɊւ����A�����^���w���X�̖��ƏA�J�x���A�A�Z��Ɗ������Ɋւ���ۑ�Ȃǂ����B
�ƍߎ҂ɐ�߂鏗���̊���
�@���E�e���̔ƍ߂Ɋւ���������v�ɂ����āA�ƍߎ҂̑唼���j���ł���A�����̊����͏��������Ƃ�������Ă���iGobeil, Blanchette, andStewart, 2016�j�B���{�̌x�@���i2003�`2022�j�́u�N�Ԃ̔ƍ߁v�ɂ��ƁA����15�N����ߘa�S�N�܂ł�20�N�Ԃɂ�����Y�@�ƌ����l���ɐ�߂鏗���̊�����20�`22���ł��邪�A���̊����͐�ォ��ɂ₩�ȑ����X���������Ă������̂ł���i���a21�N�ɂ͂����悻7.6���ł���A�����悻13�|�C���g�̏㏸�j�B���O���ɂ����鏗���ƍߎ҂̊����Ɋւ��铝�v������ƁA�Ⴆ�A�����J���O���iFBI �̔ƍߓ��v�N��j�ł́A2023�N�ɂ�����S�ߕߎ҂ɏ�������߂銄����27.5���iFBI�A2024�j�ł���A�����͍������̂̓����Q����������Ă���B���������ƍߎ҂̐��ɂ����鐫���́A�Y���{�݂ւ̓����Ґ��Ō����ꍇ�ɂ͂��傫���Ȃ�X��������A���{�̌Y���{�ݎ��e�Ґ��Ō��������̊����͗ߘa�T�N��10.6���ł���B���O���ɂ�����Y���{�݂ւ̓����҂ɂ����鏗���̊����́AFairand Walmsley�i2024�j�ɂ��ƁA�A�����J�ł�10.2���i2019�N�j�A�I�[�X�g�����A�ł�7.5���i2021�N�j�A�J�i�_�ł�5.6���i2014�N�j�A�h�C�c�ł�5.6���i2021�N�j�A�C���O�����h�ƃE�F�[���Y�ł�4.0���i2022�N�j�A�t�����X�ł�3.6���i2022�N�j�ł��邱�Ƃ�������Ă���B
�@�ߘa�U�N�Ŕƍߔ������猩��Y���i�@�̊e�ߒ��ɂ����鏗���ƍߎ҂̔䗦�́A�\�P�̂Ƃ���܂Ƃ߂���B�\�P�Ŏ����Y�@�ƁE���ʖ@�ƌ����l���ɐ�߂�N�i�^�N�i�P�\�^������Y�҂̊����́A�ߘa�T�N�̂P�N�Ԃ̓��v�Ƃ��Ă��ꂼ��̋@�ւ��������l���犄�����Z�o�������̂ł���B���̂��߁A�K�����������N�Ɍ����A�N�i�A�ٔ��A�Y���{�݂ւ̓����̑S�Ă��s����킯�ł͂Ȃ����Ƃ܂���ƁA���������l�̌o�߂��������̂ł͂Ȃ��A�����܂Ŗڈ��̐����ƂȂ�B�������A���̖ڈ��Ƃ�
�\�P�@�ߘa�U�N�Ŕƍߔ����Ɏ�����鏗���ƍߎ҂̔䗦
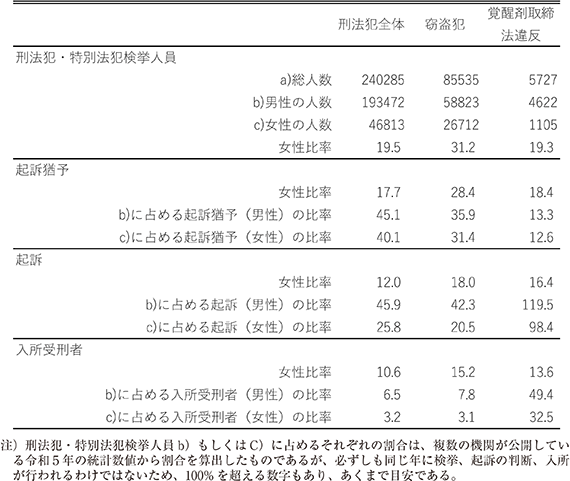
�鐔���Ŋ���������ƁA�Y�@�ƁE���ʖ@�ƑS�́A�ޓ��ƁA�o������@�ᔽ�̂�������A�����̊����͌������N�i�P�\���N�i��������Y�҂̏��ŏ������Ȃ��Ă���A���̌X���́A�Y�@�ƁE���ʖ@�ƑS�̂�ޓ��Ƃɔ�r���āA�o������@�ᔽ�Ŏア�B�܂��A�T���āA�j���ɔ�r���ď����̕��ŋN�i��Y���{�ݓ����Ɏ��銄���͒Ⴂ���A������ߎ�ʂŌ����ꍇ�A�ޓ��ƂƊo������@�ᔽ�Ƃł͈قȂ�X���������Ă���B���������ł����Ă��A�Y�@�ƁE���ʖ@�ƑS�̂�ޓ��Ƃł͌����l���̂R�����x�̐��̐l����������Y�҂ƂȂ��Ă��邪�A�o������@�ᔽ�ł͂قڋN�i����A�����l���̂����悻�R���̂P�̐��̐l����������Y�҂ƂȂ��Ă���B�����̐ޓ��Ƃ̏ꍇ�ɂ͌Y���{�ݓ����Ɏ���̂͌����҂̂��������킸���ł���A�������������i�U���߂��j�ŐN�������蕨���ł���ꍇ�����Ȃ����Ƃ��l������ƁA���ꂾ���ݔƐ��������A�w�i�ɑ����̖���������҂��Y���{�ݓ����Ɏ����Ă���Ƒz���ł���B����ɔ�r���āA�����̊o������@�ᔽ�̏ꍇ�ɂ́A���������ΌY���{�ݓ����Ɏ���m���͍����A�Ⴂ�N�ォ��Y���{�ݓ����̋@���葽������ƍl�����邪�A�Ƃ�����肩��́A�ޏ���̑������n�Ȃ�g���E�}�A�W���̖��ȂǁA����̓����������Ă���Ƒz���ł���B
�ĔƎ҂ɐ�߂鏗���̊���
�@�x�@���i2003�`2022�j���������邻�ꂼ��́u�N�Ԃ̔ƍ߁v�ɂ��ƁA�Y�@�ƌ����l���ɐ�߂�ĔƎҗ��́A����15�i2003�j�N�ɂ�35.6���ł��������A�ߘa�R�i2021�j�N��48.6���̃s�[�N����������A�ߘa�S�i2022�j�N�ɂ�47.9���ƍ����l���ێ����Ă���B�Y�@�ƌ����l���ɐ�߂�ĔƎҗ��ɂ��Ă͒j���ʂ̐��l�͌��J����Ă��Ȃ����߁A�ߘa�U�N�Ŕƍߔ����Ŏ������A�Y���{�݂ɓ���������Y�҂̓����x���ʍ\�����j���ʂŌ���ƁA�ߋ�20�N�Ԃ̐��ڂɂ����đ����̑����͂�����̂́A�u�P�x�v�̊������ɂ₩�Ȍ����X���������Ă���A��Y���J��Ԃ��҂̊������������Ă���i7-3-3-3�}�j�B�����āA���̌X���́A�j���ɔ�r���ď����ő傫���Ȃ��Ă���B����ŁA�Y���ʍ\����̐��ڂɂ����āA�����ł͌Y�����Z���Ȃ�X�����F�߂��Ă���A�ߘa�T�N�ɂ͂P�N�ȉ��ƂQ�N�ȉ���65.2�����߂�悤�ɂȂ��Ă���i7-3-3-4�}�j�B��Y���J��Ԃ��҂̊����������Ă��钆�ŌY�����Z���҂̊����������Ă��邱�Ƃ���A�S�Ă̏����̎�Y�҂��A��Y���Ԓ��ɗL���Ȏ��Ï������m���Ɏ���̂��A�Ƃ����^�₪������B�Y���̒��Z�ɂ���ĕK�v�Ȏ��Ï��������Ȃ��ꍇ�����邱�Ƃ́A�ƍߎ҂̍X���ɂƂ��ă}�C�i�X�̉e����^������B���Z���Y���̏����ƍߎ҂��J��Ԃ��Y���{�݂ɓ�������P�[�X�����炵�Ă������߂ɂ́A�Y���̒Z���҂��^�[�Q�b�g�ɂ����v���O�����ɂ��Ă��������Ă������Ƃ����߂���B�܂��A���̌Y�����Z���҂ɂ��ẮA�Y���{�݁A�ی�ώ@�̂��ꂼ��̓Ɨ������v���O��������u����̂ł͂Ȃ��A�Y���{�݂���ی�ώ@�܂ł̊��Ԃ�ʂ��Ď���v���O�������p�b�P�[�W�����Ē��邱�Ƃ��܂߁A�������Ă������Ƃ��K�v���낤�B
�����̔ƍ߂Ɏ��铹��
�@�ƍ߁E��s�����ɂ����ẮA���炭�A�����h�ł���j���ƍߎ҂�Ώۂɂ��ăG�r�f���X���n�o����Ă��Ă���A�������ɂ����ẮA���̃G�r�f���X�Ɋ�Â��āA�œK�ȕ��@����������A�j���Ɋւ�炸����������Ă����B�������A�d�v�ȕ��ގ��Ƃ��ăW�F���_�[������ɂ��ւ�炸�A�j���̈Ⴂ���l�������ɁA�����ƍߎ҂ɂ������������s�����Ƃɂ��āA�����̌����҂��٘_�������Ă����i�Ⴆ�ABloom, Owen andCovington, 2005�j�B�����Ŏ����ꂽ�ۑ�́A���{�̋��������ɂ����Ă��F�߂���B
�@�����ƍߎ҂��j���ƍߎ҂Ɠ��l�ɑ��l�ȑ��݂ł���ɂ��ւ�炸�A���I�ȏ����ƍߎ҂̑���������₷���BHoltfreter, Pusch and Golladay�i2022�j�́ADaly ��1992�N�Ɏw�E���������ƍߎ҂̉��I�ȃ��f�����u�Ⴂ�����́A�@�������ɉƒ���ɂ�����g���E�}��\�́A�s�҂��o�����A�A�s�҂��瓦��邽�߂ɉƂ��o�āA�B�X���Ŕ��t��Ȃǂ̔ƍ߂Ɏ����߂�悤�ɂȂ�B�E�E�E�����āA��Q�Ɖ��Q�̃T�C�N�����J��Ԃ��A�₪�ČY���i�@�V�X�e���Ɋւ��悤�ɂȂ�B�v�Ƃ������̂ł���ƋL�q���Ă���B�܂��ADaly ��1992�N�Ɍ��o�����������ƍ߂Ɏ��铹�̂S���ނ́A�H��istreet�j�A��Q�Ɖ��Q�iharmed and harming�j�A�s�҂��ꂽ�ibattered�j�A�ɂ܂��idrag connected�j�ł���Ƃ��A��ɁA�T�߂̓��Ƃ��āA�o�ϓI���@�ieconomically motivated�j��������ꂽ���Ƃ��L�q���Ă���B�H��̏����́A�s�ғI�����瓦���o���A���łƂȂ�A�H�㐶�����������߂ɔƍ߂��s���B��Q�Ɖ��Q�Q�̏����́A�c�����ɋs�҂��A���Ƃ�Ƃ����������ɒu����Ă���A���N��s�ŕ⓱���ꂽ�o�������B�s�҂��ꂽ�Q�̏����́A�e���ȊW�̒��ŋs�҂��Ă���B�ɂ܂�鏗���́A�Ƒ���e���ȊW�̒��Ŗ��g�p������A�����A�̔������肷��B���̂S�Q�̔ƍ߂Ɏ��铹�͏����ƍߎ҂ɓ��L�̓��ƂȂ��Ă���A������̌Q�ł������ƍߎ҂̐�����ɂ͉ƒ���ł̋s�҂�\�̖͂�肪����B�����ɑ��A�o�ϓI���@�̏��������ɂ́A������ɔ�s�Ҍo�����������A�o�ϓI���@����ƍ߂Ɏ���B
�W�F���_�[�ւ̔z��
�@�����̔ƍ߂Ɏ��铹�Ɋւ��錤�����_�@�Ƃ��āA�W�F���_�[�ɔz������5�A�Z�X�����g�⏈������������Ă����B�ƍ߂Ɏ��铹�Ɋւ��錤���ł́A���܂��܂ȃW�F���_�[�ɔz�������v�������o����Ă����B�Ⴆ�A�����ƍߎ҂ɂ͎������̃g���E�}�̌���L����҂��������Ƃ͑����̌����Ō��o����Ă���iBrowne, Miller and Maguin, 1999; Tamand Derkzen, 2014�j�B�ߘa�U�N�Ŕƍߔ����Ŏ��������ʒ����̌��ʁi7-5-3-6�}�j�ɂ����Ă��A�������t���̌��Ƃ��Ď�����鎙���s�҂Ƃ����鍀�ڂ�����ƁA�g�̓I�s�ҁi����32.7���A�j��36.6���j��l�O���N�g�F�g�̉��̐��b�����Ă��炦�Ȃ������i����9.8���A�j��8.9���j�ł͒j���ƍߎ҂Ə����ƍߎ҂œ����x�̊������������A�S���I�s�ҁi����39.2���A�j��30.4���j�A���I�s�ҁi����6.0���A�j��1.7���j�A�l�O���N�g�F�\���ɋC�Ɋ|���Ă��炦�Ȃ������i����25.6���A�j��18.6���j�ւ̊Y���́A�j���ƍߎ҂Ɣ�r���ď����ƍߎ҂ō����Ȃ��Ă����B���������������̋s�Ҕ�Q�̖��́A�N���ȍ~�̐��_�ی��ɑ傫�ȉe����^���邱�Ƃ��w�E����Ă���A�j���ƍߎ҂Ɣ�r���ď����ƍߎ҂ɂ����Đ��_�ی���̖��������Ɛ\������҂��������Ɓi�ߘa�U�N�Ŕƍߔ����A7-5-2-8�}�E7-5-2-9�}�j�Ƃ��֘A���Ă���B
�@�����̌����ŁA�����̔ƍ߂ɓ��Ɋ֘A����v���Ƃ��āA�玙�ӔC�A�g���E�}�o���A�����^���w���X�Ƃ������v�����������Ă���A�����̗v���̂ق��ɂ����p�A���Љ�I�Ȓ��ԊW�A�ے�I�ȉƑ��^�v�w�̌q����Ƃ������v���ւ̊Y�����j�����������ɂ����đ������Ƃ��w�E����Ă���iGower, Morgan & Saunders, 2024�j�B
�W�F���_�[�ɔz�������Ĕƃ��X�N�̃A�Z�X�����g
�@�Ĕƃ��X�N�A�Z�X�����g�c�[���ɂ����ẮA�唼��j������߂�T���v����ΏۂɊJ������Ă��邱�Ƃ���A�������ƍ߂Ɏ��铹���w�Ǎl������Ă��Ȃ����ƁA�j���ɂ�����ĔƗ��̍����̈Ⴂ���l������Ă��Ȃ����ƂȂǂ���A�����ƍߎ҂̃��X�N���ߑ�]�����邨���ꂪ���邱�Ƃ��w�E����Ă���B�唼��j������߂�T���v����ΏۂɊJ�����ꂽ�c�[���ɃW�F���_�[�Ή����q6��lj����ă��X�N��]�����ׂ����A�W�F���_�[���l�������ɁA�܂�W�F���_�[�E�j���[�g�����igenderneutral�j�Ȃ��̂Ƃ��āA�W�F���_�[�Ή����q�̍��ڂ�lj����邱�ƂȂ��j�����ʂɗ��p���ׂ����ɂ��ċc�_���s���Ă���B
�@�Ⴆ�A�ƈ����j�[�Y�ƂȂ�54�̃_�C�i�~�b�N���X�N�v���𑪒肷��LSI-R�iLevel of Service Inventory- Revised�j �ɂ��ẮA Smith,Cullen & Latessa�i2009�j���A����LSI-R �̌��ʂƏ����ƍߎҁiN =14,737�j�̍ĔƂƂ̊W���K�͂ȃ��^���͂ɂ���Č������ALSI-R ���W�F���_�[�E�j���[�g�����ȃc�[���Ƃ��Ēj���ɓ����悤�ɗ��p�ł��邱�Ƃ������Ă���B�܂��AWolf, Mayer, Steiner, Franke, Klein, Streb,& Dudeck�i2023�j�́A���_��Q��L���鏗���ƍߎ�525�l��Ώۂɂ��������̒��ŁA�e���ȊW�ɂ�����@�\�s�S�A�����^���w���X�̖��A�e�̃X�g���X�A���l�̐g�̓I�s�ҁA�n���Ƃ������W�F���_�[�Ή����q���ĔƂƋ����֘A���邪�ALSI-R �̕��ސ��x����Ɋ�^�����W�F���_�[�Ή����q�́A�������p�[�\�i���e�B��Q�A���Љ�p�[�\�i���e�B�A�x���̂Ȃ��p�[�g�i�[�A�n���ł���A���̐��x�̑����͂킸��2.2���ł��������Ƃ���A�W�F���_�[�Ή����q��lj�����K�v���ɂ��ċ^���悵�Ă���B
�@����������ŁAvan Voorhis�i2012�j�́A�����̃��X�N�]���c�[���ɃW�F���_�[�Ή����q�������邱�ƂŁA�i�@�Ɋ֗^���鏗���ɑ���Ó��������܂������Ƃ���Ă���B�܂��AHoltfreter, K., & Cupp, R.�i2007�j�́A�ƍ߂̔w�i���j���ƍł��ގ����Ă���Ǝv���鏗���ƍߎ҂ɑ��Ă͂��Ȃ�L���ł���悤�����A�����ƍߎғ��L�̔ƍ߂ւ̓������ǂ鏗���ɑ��Ă͂����Ƃ͂����Ȃ����Ƃ��w�E���Ă���B���^�A�i���V�X�̎�@��p���������ł́AGobeil, Blanchette, and Stewart�i2016�j���A���v��22,000�l�̏����ƍߎ҂�ΏۂƂ���37�����Ŏ����ꂽ38�̌��ʗʂ������������ʁA�W�F���_�[�ɔz�����������ƃW�F���_�[�ɂƂ���Ȃ��W�F���_�[�j���[�g�����ȏ����Ƃł��̌��ʂɈႢ�͂Ȃ��������A��莿�̍������@�_�ōs��ꂽ������18�̌��ʗʂɍi��ƁA�W�F���_�[�ɔz�����������̕����A��菗���ƍߎ҂̍ĔƂ̌����Ɍq�����Ă������Ƃ������Ă���B
�@���̂悤�ɖ������錋�ʂ�������Ă��錤�����T�ς���ۂ̗��ӓ_�Ƃ��āASaxena, Messina, and Grella�i2014�j�́A�����ƍߎ҂̃T���v���̏������̖���A���@�_�I�E���v�I�Ȍ������Ɍ����錤���������Ƃ�����肪���邽�߁A���ʂ݂̂����ĒP���ɔ�r���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��A�Ǝw�E���Ă���B�܂��A�����������̑��݂���A�����ƍߎ҂ɓ��L�̗v����lj����Ă������ȃc�[���Ɏd���Ă邱�ƂɌ��E������\��������i��]�A2023�j�B
�W�F���_�[�ɔz����������
�@�W�F���_�[�ɑΉ������ƈ����j�[�Y�́A�ƍ߂ݏo�����X�N�v���ł͂Ȃ��iAndrews and Bonta, 2010�j�Ƃ���邪�A�W�F���_�[�́u�r�b�O�S�v�܂��́u�Z���g�����W�v�̏����ւ̔�������}���ƍl�����Ă���B
�@���Ăɂ����ẮA�W�F���_�[�ɓ������������v���O��������������Ă��邪�A���ꂪ�F�m�s���v���O�����Ƃ��ĊJ������Ă���ꍇ�ɂ́A��ʓI�Ȕ������������w�E����s���A�Љ�w�K�A�F�m�s���̗l���ɂ�����x�K�����邱�Ƃ��w�E����Ă���iVan Voorhis, 2012�j�BBlanchette ��Brown�i2006�j�́A�W�F���_�[�ɓ������������v���O�����ɂ������ʓI�Ȕ������������A�u�W�F���_�[�ɑΉ����������������ł́A��ʓI�ɁA���Î҂��A�t�F�~�j�X�g�̓N�w�ƎЉ�w�K���_�Ɋ�Â��\�������ꂽ�s��������A�w���݂���ՂƂ������f���x�Ƃ��ċ����I���G���p���[�����g������@�Œ���Ɠ����ɁA�����������ȃA�v���[�`���̗p�����ꍇ�ɁA�œK�Ȏ��Ô�����������v�ƍĒ莮�����Ă���B
�@���{�ɂ����Ă��A�ꕔ�̎{�݂ɂ����āA��N�����̖ƍߎ҂ɓ��������v���O�����̎��H���s���Ă���B���̎��H�ł́A���ÓI�Ȋ��ɂ����鏈�����s���Ă���A����I�Ȏ�g�ł���B���������V������g�̌��ɂ͂����������Ԃ�v���邩������Ȃ����A�g �ĔƁh ��g �ē��h�Ƃ������w�W�����łȂ��A�Љ�̒��œK���I�ɐ�����͂Ƃ��Ăǂ̂悤�ȋ��݂�g�ɂ�����A�L������ł����̂��Ƃ��������Ƃ��]���ɉ����Ă������Ƃ��ł���Ƃ悢�ƍl������B���݂̓��X�N���ɘa����ی�v���ƂȂ邽�߂ł���B�����ɓ��������ۑ�Ƃ��ẮA��D��D�P�A�q��Ă̖��Ȃǂ������邱�Ƃ������A�����ƍߎ҂������Y���{�݂̑����ł́A�����ɓ��������ۑ�͈�ʉ��P�w���̈�Ƃ��Ď��g�܂�Ă���B�������A�����ƍߎ҂̔ƍ߂Ɏ���o�H�Ŏw�E�����悤�ȗv����A�Ĕƃ��X�N�A�Z�X�����g�ɂ����Č�������Ă���w�i�v���ɂ��Ă��A�ϋɓI�Ɉ����Ă������Ƃ��K�v�ł��낤�B�܂��A���������ƍߎ҂ł��ƍ߂Ɏ��铹���قȂ�ꍇ������悤�ɁA�ƍ߂����Ȃ��ŎЉ�œK���I�ɐ����铹�����ꂼ��قȂ���̂����邾�낤�B���������o���܂����v���O�������������Ă����K�v�����邩������Ȃ��B�����́A�j���Ɣ�r���ďA�Ɨ����Ⴍ�A�K�J���������Ƃ����Љ�̒��A�����O�ɏA�J���Ă��Ȃ������҂������A�����ƍߎ҂̒��ɂ͏A�J�ӗ~�������Ȃ��҂����Ȃ��炸���邱�Ƃ���A�Љ�̒��œK���I�ɐ����铹���ƂɏA�J�x���̂��߂̃v���O�����̂�������l���Ă������Ƃ��K�v��������Ȃ��B�����A�����ƍߎ҂���������{�݂͏��Ȃ��A�����ƍߎ҂̏����Ɋւ��l���͌����Ă��邱�Ƃ���A���ꂼ��̎{�݂̎�g�ɗ��܂点���A�W�F���_�[�Ή����q�Ɋւ�鏈���ɂ��ẮA���ꂼ��̃e�[�}�ɂ��Ē��j�ƂȂ�v���O������莮�����Ă������Ƃ��K�v�ƂȂ邾�낤�B
�@Leote de Carvalho, Duarte and Gomes�i2023�j�́A�|���g�K���̏����ƍߎ�49�l�ɑ���C���^�r���[��ʂ��āA�����ƍߎ҂���������̔ƍߍs�����ǂ̂悤�ɍ\�����A�������Ă��邩�ɂ��Č������s�������ʁA�Ⴂ�����ƍߎ҂ƍ���̏����ƍߎ҂ł͔ƍ߃p�^�����قȂ��Ă��邱�Ƃ����o����Ă���B���̂��Ƃ́A�ߎ��ƍ߂Ɏ��铹�݂̂Ȃ炸�A���̐l�̐��U���B�̒i�K�ʂɕK�v�ƂȂ�ۑ肪�قȂ邱�Ƃ��������Ă���B����҂̏ꍇ�ɂ́A�A�J�͂Ȃ��A�Ƌ��ŁA�Љ�I�ɌǗ�������Ԃɂ��邱�Ƃ��傫�Ȗ��ƂȂ��Ă���B����̔ƍߎ҂ɂ́A�g�̂̋@�\���x���鏈���݂̂Ȃ炸�A�Љ�̒��łǂ̂悤�ȓK����ڎw���̂��ɂ��ċ�̓I�ȃC���[�W���������A�����ڎw�����߂ɕK�v�ȋ��݂�g�ɂ��Ă��炢�A�Љ���ň�ʂ̍���҂���T�[�r�X�⎑���ɓI�m�Ɍq���Ă������Ƃ��ۑ�ƂȂ�B���݁A�Y���{�ݓ��ŎЉ�A�������s���Љ���m�̌l�̗͗ʂɗ��镔�����傫�����A����A�s���Ƃ̘A�g����苭�������A���X���[�Y�Ȍ`�ō���ƍߎ҂��Љ�I�Ȏ����ƌ��т��邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����ƍl������B
�����^���w���X�̖��ƏA�J�x��
�@�j���ƍߎ҂Ɣ�r���ď����ƍߎ҂Ń����^���w���X�̖�������Ă���Ɛ\������҂������i�ߘa�U�N�Ŕƍߔ����A7-5-2-9�}�j�A�������̋s�҂₻�̌�̌��ۑ����z��҂���̖\�̖͂��������҂���萔����A���ꂪ�����̖ƍߎ҂ł������ꍇ�ɂ͊������傫���Ȃ��Ă����i���A7-5-3-5�}�A7-5-3-6�}�j�B�܂��A�����̖ƍߎ҂Ŏ����s�ׂ̌o�����������Ȃ��Ă����B�i���A7-5-3-4�}�j�B���������g���E�}��\�͔�Q�̌o���́A�����^���w���X�̖��Ƌ����֘A���Ă���A�\�ʏ�̃����^���w���X�̖��ɑΏ����邾���ł͂Ȃ��A���̔w�i�ɂ���g���E�}��\�͂̔�Q��ڌ��̖��������K�v�������傫���Ȃ邾�낤�B���s���̔w��ɂ��������g���E�}�o��������\���ɔz������g���E�}�E�C���t�H�[���h�E�P�A�̍l�������̂����A�����ƍߎ҂��������s���������Ă������Ƃ��d�v�ł���B
�@���̂ق��A�ޓ���K�Ȃ�L���鏗���ƍߎ҂̔w�i�v���ɐېH��Q������ꍇ�������ɂ��ւ�炸�A�Y���{�݂ł͑̏d�m�ۂ̂��߂̈�ÓI�ȃP�A�͐��x������Ă��邪�A�ېH��Q���^�[�Q�b�g�ɂ����v���O�����͂Ȃ��B����䂦�A�Љ���̎����ɗ���Ȃ���Ȃ�Ȃ����A�Љ���̎������L�x�ɂ���킯�ł͂Ȃ��Ƃ���������B�ېH��Q�䂦�ɐޓ�������҂̏ꍇ�A��ʓI�Ȑޓ��̖��݂̂����グ�Ă�������P�ɂ͎���Ȃ��B�ޓ��̏ꍇ�ɂ͑ߕ߂���Ă�������Ɏ��銄�����������Ȃ��������Ƃ��l������ƁA�w�i�ɂ���ېH��Q�̖�肪���Ȃ蒷���ɂ킽���Ă���A���[���Ȏ҂ƂȂ��Ă���\��������B�ېH��Q�̖��ɑ��A�{�ݓ��Ő������邽�߂̈�ÓI�P�A�݂̂Ȃ炸�A�S���I�ȉ�����������Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�܂��A�ېH��Q�Ɋւ��鎡�Ï����Ɋւ����含�����E�����琬���邱�Ƃ��K�v�ƂȂ邾�낤�B
�@�������������^���w���X�̖��́A�ȒP�ɉ���������̂ł͂Ȃ��A���Âɂ͒����̊ւ���v���邾�낤�B�����āA�����^���w���X�̖��͏A�J����肵�������̖��Ƃ��֘A����B���̐l�̃y�[�X�œ������Ƃ��T�|�[�g�ł���悤�Ȑl�ޔh���ƂȂǂ̎Љ���ɂ��܂��q�����������A����͎Q�l�ƂȂ邾�낤�B�܂��A��t����̐f�f���邱�Ƃœ�����Љ�T�[�r�X�𗘗p�ł���悤�A��Ë@�ւƌq���邱�Ƃ͏d�v�ł���A�Љ���m�̗͂����߂���Ƃ���ł���B�܂��A�f�f�������Ȃ��ꍇ�ł��A���_�I�ɕs����ɂȂ����Ƃ��ɑ��k�ł����������Ă������Ƃ��d�v�ƂȂ�B���݁A�X���ی�{�݂ɂ����āA�t�H���[�A�b�v���Ƃւ̎�g���s���Ă��邪�A�{�l�����������Ȃ��ł���ꍇ�ɂ��A�E�g���[�`�ɂ��A�������Ƃ��Ȃǂɖ{�l����b���ł���ꏊ��q��������邱�Ƃ��ł���A�ĔƖh�~�ƎЉ�K���̑��i�Ƀv���X�̉e���������炷���낤�B
�A�Z��Ɗ������Ɋւ���ۑ�
�@���݁A�ϋɓI�ɉ��o�����s���A�ی�ώ@�ɂ��Љ���ł̓K�����T�|�[�g�ł�������ւ̎�g����芈���ɍs���Ă���B����ɂ��A�����̉��ߕ����������̏ꍇ�ɂ͂W���ɋ߂��l�������Ă���A�A�Z�悪�m�ۂł����҂��������Ƃ��������Ă���B���҂炪�s���������������Y���{�݂̒����ł́A������̎{�݂ł��Ƒ�������l�ƂȂ��Ă���ꍇ���������Ƃ�������Ă���B�����ƍߎҖ{�l�ɑ��鎡�Ï����ł́A�{�l�����ƈ����j�[�Y�ւ̓����|�����s���A���݂��g���邱�Ƃ͂ł��邩������Ȃ����A���̉Ƒ���z��҂ȂǁA�{�l���߂���ɂ͓����|�������邱�Ƃ͂Ȃ��B�W�F���_�[�ɓ��������ƍ߂Ɏ��铹�����ǂ��������ƍߎ҂̔w�i�v����A�����҂Ƃ̖��p�Ȃǂ̏ꍇ���l����ƁA�A�Z�悪�����O�Ɠ����ł������ꍇ�A���̏ꏊ�ɒ����ɖ߂邱�Ƃ��őP�Ȃ̂��A�ɂ��Ă͌����̗]�n�����邩������Ȃ��B�����̋A�Z��̖��ɂ��Ăł��邱�Ƃ����邩�ɂ��ẮA���������l���Ă������Ƃ��K�v�ƂȂ邾�낤�B
�܂Ƃ�
�@�ȏ�A�{�����O���[�v�ŏ�������������Y���{�݂����@�Ƌc�_���s�������ʂ܂��āA�ߘa�U�N�Ŕƍߔ����̓��ʒ����Ŏ����ꂽ�����ƍߎ҂̓��W���玦������鍡��̉ۑ�ɂ��Ď������B�������ӌ��́A�����҈�l�̈ӌ��ł���A�g�D���\������̂ł͂Ȃ��B�ߘa�U�N�Ŕƍߔ����̓��ʒ����̂悤�ɁA������x�̐��ʂ������ď����ƍߎ҂̓��������������͕̂M�҂̒m����荑���ł͖w�ǂȂ��A���ɋM�d�ł���B�������Ȃ����̂ɂ��܂���ĂĂ����Ȃ����������ƍߎ҂ɂ��āA�~�ς��ׂ��m���͂܂������A�����ƍߎ҂̑��l���ɒ��ڂ��������ւ̓W�J�A�����ւ̉��p���]�܂��B
�ӎ�
�@�{������JSPS �Ȍ��� JP22H00932�̏����������̂ł��B
�i�x�@���Ȋw�x�@�������ƍߍs���Ȋw�����j
����
Andrews, D. A., & Bonta, J.�i2010�j. Rehabilitating criminal justice policy and practice. Psychology, Public Policy, and Law, 16�i1�j, 39.
Blanchette, K., & Brown, S. L. �i2006�j. The assessment and treatment of women offenders: An integrative perspective . John Wiley & Sons.
Bloom, B. E., Owen, B. A., & Covington, S. �i2005�j. Gender-responsive strategies for women offenders: A summary of research, practice, and guiding principles for women offenders. US Department of Justice, National Institute of Corrections.
Browne, A., Miller, B., & Maguin, E. �i1999�j. Prevalence and severity of lifetime physical and sexual victimization among incarcerated women. International journal of law and psychiatry, 22�i3-4�j, 301-322.
de Vogel, V., de Vries Robbé, M., van Kalmthout, W., & Place, C. �i2014�j. 'Female Additional Manual'�iFAM�j: Additional guidelines to the HCR-20v3 for assessing risk for violent women. Van del Hoeven Kliniek, https://irp-cdn.multiscreensite.com/21b376df/MOBILE/pdf/ fam+to+be+used+with+hcr-20+version+3+-+english+version+2014.pdf. Downloaded on 22/1/2024.
Fair, H., & Walmsley, R.�i2024�j. World prison population list. ICPR. https://www.prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/world_female_imprisonment_list_5th_edition.pdf, downloaded on 11/11/2024.
Federal Bureau of Investigation �i2024�j. Arrestees Adult and Juvenile Age Category by Arrest Offense Category 2023., https://cde.ucr.cjis.gov/ LATEST/webapp/#, downloaded on 18/10/2024.
Gobeil, R., Blanchette, K., & Stewart, L. �i2016�j. A meta-analytic review of correctional interventions for women offenders: Gender-neutral versus gender-informed approaches. Criminal Justice and Behavior, 43�i3�j, 301-322.
Gower, M., Morgan, F., & Saunders, J. �i2024�j. Gender responsivity in the assessment and treatment of offenders. Psychiatry, Psychology and Law, 31�i4�j, 587-611.
Holtfreter, K., & Cupp, R.�i2007�j. Gender and risk assessment: The empirical status of the LSI-R for women. Journal of contemporary criminal justice, 23�i4�j, 363-382.
�x�@���i2017�`2022�j.�@�N�Ԃ̔ƍ߁i����15�N�̔ƍ߁`�ߘa�S�N�̔ƍ߁j�A�x�@���D
Leote de Carvalho, M. J., Duarte, V., & Gomes, S.�i2023�j. Female crime and delinquency: A kaleidoscope of changes at the intersection of gender and age. Women & Criminal Justice , 33�i4�j, 280-301.
Menna Gower, Frank Morgan & Julie Saunders�i2024�j Gender responsivity in the assessment and treatment of offenders, Psychiatry, Psychology and Law, 31:4, 587-61
��]�R���i2023�j. Gender �| Neutral �Ȕƍߎ҂̃A�Z�X�����g�E�����ɂ��čl����A�����ƍߖ�茤����\�����A2023�N�S��16���D
Saxena, P., Messina, N. P., & Grella, C. E.�i2014�j. Who benefits from genderresponsive treatment? Accounting for abuse history on longitudinal outcomes for women in prison. Criminal justice and behavior, 41�i4�j, 417-432.
Smith, P., Cullen, F. T., & Latessa, E. J.�i2009�j. Can 14,737 women be wrong? A meta - analysis of the LSI - R and recidivism for female offenders. Criminology & Public Policy, 8�i1�j, 183-208.
Tam, K., & Derkzen, D. �i2014�j. Exposure to trauma among women offenders: A review of the literature �iResearch Report, R333�j. Ottawa, Ontario: Correctional Service of Canada .
Van Voorhis, P.�i2012�j. On behalf of women offenders: Women's place in the science of evidence-based practice. Criminology & Pub. Policy, 11 , 111.
Wolf, V., Mayer, J., Steiner, I., Franke, I., Klein, V., Streb, J., & Dudeck, M. �i2023�j. The predictive accuracy of the LSI-R in female forensic inpatients-Assessing the utility of gender-responsive risk factors. International Journal of Environmental Research and Public Health, 20�i5�j, 4380.
��
�P�@���̌����O���[�v�ɂ́A�{���v�h�A���X�q�A���{�����A���{���a�A�����N�v�A�ēc��A�n糘a��������A����炪���S���ĖK�⒲�������{���Ă���B
�Q�@�����Y���{�݂���̓I�ɋ�����ƁA�Ȗ،Y�����A�}���Y�����A�a�̎R�Y�����A�⍑�Y�����A�[�Y�����A�D�y�Y���x���A�����Y���x���A�L���Y���x���A�����Y���x���A��A��Љ�A���i�Z���^�[�̏������e���A���Ð�Y�����̏������e���A���I�Љ�A���i�Z���^�[�̏������e����12�{�݂ł���B
�R�@�����{�݂ł���Ȗؖ�����A�ÏC��r�엾�A���S��A�������A���S�V�ƁA���{�莛�������A�~�����A�j���{�݂W�̂����R�{�݁A��J�������A�[����A�E�B�Y�L����K�₵���B
�S�@�j���Y���{�݂Ƃ��āA�D�y�Y�����A�����Y�����A����Y�����A����Y�����A�x�R�Y�����A����Y������K�₵���B
�T�@�W�F���_�[�ɔz�������igender informed�j�Ƃ������t�̂ق��A�W�F���_�[�ɑΉ������igender responsive�j�Ƃ������t���p�����邪�A�����̌��t�̎g�p�͌����҂╶���ɂ���ĈقȂ��Ă���A�قړ��`�Ƃ��ėp�����Ă�����̂ł���B
�U�@�Ⴆ�AHCR-20��Female Additional Manual�ide Vogel, de Vries, van Kalmthout, & Place, 2014�j�ɂ́A���j���ڂƂ��āAH11���t�AH12�{�獢��AH13��N�ł̔D�P�AH14���E��}�^�������lj�����AH7�p�[�\�i���e�B��Q��H8�g���E�}�o���ɏ��������̃K�C�h���C�����t������Ă���B�܂��A�Տ����ڂƂ��āAC6���ݓI�ȑ���I�s���AC7�Ⴂ�����S�̍��ڂ��A���X�N�Ǘ����ڂƂ��āAR6���̂���{��ӔC�AR7���̂���e���ȊW���������Ă���B