
トップページ > 刑事政策関係刊行物:犯罪白書 > 官庁データの利活用による犯罪分析の可能性─令和元年版犯罪白書を読んで
犯罪白書
官庁データの利活用による犯罪分析の可能性─令和元年版犯罪白書を読んで
岡邊 健
1 はじめに令和元年版犯罪白書(以下本稿では「本白書」とする。)は,例年の犯罪白書とは異なり,特定のトピックに関する特集を置かず,全編を「平成の刑事政策」の特集として,この30年間の犯罪動向等について,その変遷を振り返るスタイルをとっている。本白書は「はしがき」でも述べられているように,「犯罪情勢の定点観測を行うための素材として,効果的な刑事政策の立案の基盤となるとともに,各種犯罪・犯罪者に対する各種政策の現状を知り,犯罪の抑止・再犯防止,犯罪者の処遇等に関する様々な問題に引き続き取り組む上での基礎資料」となるだろう。
本稿では,本白書のいくつかの「読みどころ」を取り上げて,その内容を簡潔に紹介するとともに,筆者の問題関心に沿って,紹介されているデータの活用法のいくつかを提案してみたい。
2 刑法犯発生率に関する都道府県別の分析
本白書の第2編「平成における犯罪・少年非行の動向」は,第1章「犯罪の動向」と第2章「少年非行の動向」,それに第3章「諸外国における犯罪動向」の3章構成である。とりわけ目を引くのが,第1章第1節で,認知件数と発生率(人口10万人当たりの認知件数),それに検挙人員とその人口比(人口10万人当たりの検挙人員)について,それぞれ元年,15年,30年の値が都道府県別に示されている箇所である(2-1-1-7図・2-1-1-8図)。
ここ数年の犯罪白書の本文中で,都道府県別の数値の分析がなされることは,なかったと思われる。管見の限りでは,平成10年代に,何度か特集のなかで分析されている。バックナンバーをみると,たとえば,平成14年版白書の特集(暴力的色彩の強い犯罪の現状と動向)では,傷害の認知件数に関する若干の分析がなされていたし(たとえば,8年からの5年間で全国的に上昇しているが,とりわけ宮城・栃木・三重・大阪・沖縄の各府県で上昇幅が大きかったとされている。),平成15年版白書の特集(変貌する凶悪犯罪とその対策)では,殺人・強盗の地域差と過去20年の地域的変動について言及されていた(たとえば,強盗の発生率が東京及びその周辺の4県と大阪で際立って高く,20年間の変化をみると大都市のベッドタウン地域で強盗が著しく増えており,東京圏ではドーナツ化現象が生じている(東京の発生率は全国平均を下回る)とされている。)。また,平成18年版白書の特集(刑事政策の新たな潮流)では,一般刑法犯(刑法犯全体から道路上の交通事故に係る業過(現在は刑法から分離されている)を除いたもの)の変化について,昭和48年の認知件数を100とした指数による分析がなされていた(たとえば,一般刑法犯が戦後最多を記録した14年の指数は,主に首都圏,関西,中京地域等大都市部とその周辺できわめて高く,千葉と岐阜では400を超えたとされている。)。
本白書第2編第1章の都道府県別分析によれば,元年と比べたとき,全都道府県で15年の発生率は上昇,30年の発生率は低下している(2-1-1-7図)。また,検挙人員の人口比も同様に,元年と比較すると,15年はほとんどの都道府県で増加しているのに対して,30年はほとんどの都道府県で減少している(2-1-1-8図)。本文中では,これ以上踏み込んだ記述はみられなかったが,都道府県別のデータからは,さまざまな示唆を得ることができると思われる。
一例として,上記3カ年分の発生率の値をもとに,クラスタ分析を用いて都道府県を分類することができる。試みに,グループ間平均連結法による階層的クラスタ分析にかけたところ(距離はユークリッド平方距離),図Aのように,6つのクラスタを析出することができた。クラスタ1は,元年には1300〜1800で平均かそれを上回る水準であったが,15年には1600〜2100を示し平均を下回った県(その間の増加率は3〜49%),クラスタ2は,元年に1100未満,15年に900〜1900でいずれも平
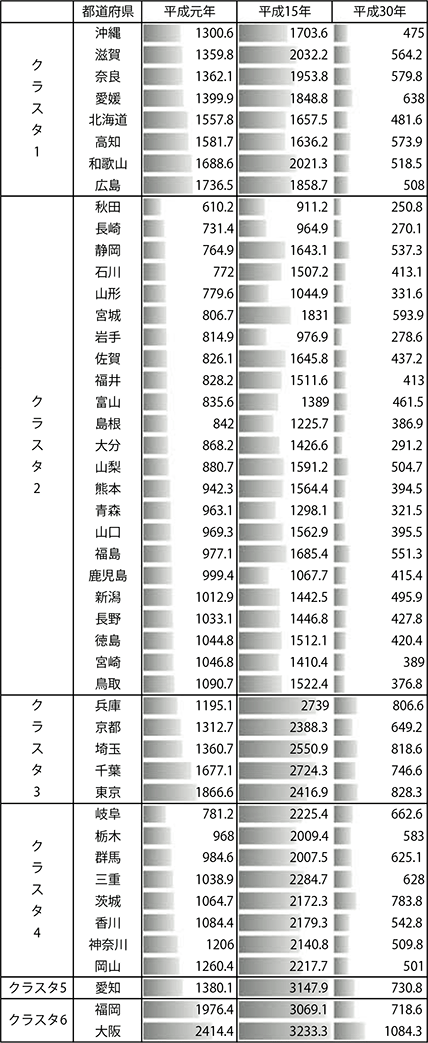
図A 平成元年・15年・30年の刑法犯発生率に基づく都道府県のクラスタリング
均を下回っている県(同7〜127%),クラスタ3は,元年に1100〜1900なのに対して,15年は平均を大きく上回る2300〜2800を示した都府県(同29〜129%),クラスタ4は,元年に700〜1300と平均を下回っていたが,15年に2000〜2300と急増した県(同76〜185%),クラスタ5は,元年から15年にかけて128%もの増加を示し,15年に3000を超えた県(愛知県のみ),クラスタ6は,元年も15年も平均を大きく上回り,それぞれ1900〜2500,3000〜3300を示している府県(同34〜55%)である。確かに,元年と比べたとき,全都道府県で15年の発生率は上昇しているのだが,上昇率を詳しくみれば,その変化の態様は,多様である。3%余りのわずかな増加にとどまっている県(クラスタ1に含まれる高知県)もあれば,185%増(すなわち2.85倍)という激増といってもよい県(クラスタ4に含まれる岐阜県)もある。
本文中でも示されているように,扱われている都道府県別のデータは,警察の管轄区域に従って作成されたものであり,ある県で認知・検挙の対象になったからといって,その犯罪で検挙された人物が当該県に在住しているとは限らない。この点には留意が必要であるが,都道府県別の分析は,犯罪発生の地域格差を把握する上で,有用であると思われる。上で試みたクラスタ分析は,あくまで一例にすぎないが,犯罪の地域差をデータをもとに可視化することによって,犯罪の原因・背景や対応策を考えるための有力な手掛かりとすることは,可能だと思われる。今後の犯罪白書でも,何らかの形で地域差に着目した分析が示されることを期待したい。
3 裁判員裁判の実施状況の分析
本白書第3編「平成における犯罪者・非行少年の処遇」は,第1章「犯罪者の処遇」,第2章「非行少年の処遇」,第3章「刑事司法における国際協力」から成る。159頁にわたって膨大な情報量が盛り込まれているが,筆者が特に注目したのは,第1章第3節の裁判員裁判に関する記述(125〜131頁)である。平成期の刑事政策上の最大の変化といえば,裁判員裁判の導入であると言って差し支えないであろうから,「平成の刑事政策」を振り返る本白書でこのトピックに紙幅が割かれるのは,当然であろう。
本文では,裁判員裁判の概要が述べられた後に,裁判員裁判の実施状況について整理されている。30年までに,裁判員裁判対象事件の第一審で扱われた事件は,新規受理人員ベースでみれば,総数が1万3715人,このうち訴因の罪名別にみると,多い順に強盗致傷(23.4%),殺人(21.8%)などとなることが紹介されている(3-1-3-8表)。また裁判の態様について,22年,26年,30年の数値が本文中で示されている。審理期間の平均は,それぞれ8.3月,8.7月,10.1月で,近年若干長期化していることが示唆されており,開廷回数の平均は,それぞれ3.8回,4.5回,4.8回で,こちらも増加傾向がみてとれる。いずれも,司法統計年報や裁判所のウェブサイトで公開されている「裁判員裁判の実施状況」に関するデータで発表される(または発表済みの)数値ではあるが,一般市民が手に取る犯罪白書のなかで,これらのデータを紹介することには,大きな意義があると考えられる。
筆者がとりわけ興味深く感じたのが,裁判員裁判と裁判官裁判の科刑状況別構成比のデータ(3-1-3-10図)である。裁判所ウェブサイトでは,「裁判員制度10年の総括報告書」等の形で,同様のデータが公開されてはいるが,本白書では,裁判員裁判については,21〜28年の累計が,裁判官裁判については,21〜26年(27年以降の終局人員はいない。)の累計が,殺人,強盗致傷,傷害致死,強姦致死傷の4つの罪名について,それぞれ比較検討されている。29年7月に施行された改正刑法において,旧強姦致死傷の法定刑の下限が引き上げられたことなどを考慮して,このような比較を行なった旨が,本文で説明されている。
殺人については,3年以下の刑期(執行猶予付を含む。以下同様。)の構成比が,裁判員裁判で26%,裁判官裁判で17%であり,前者の方が高い。保護観察付全部執行猶予(以下では「観察付猶予」と記す。)の構成比が裁判員裁判の方で高くなっていることも,注目に値する(欲を言えば,殺人は既遂と未遂を区別してデータを示したほうがよかったかもしれない。)。強盗致傷や傷害致死についても同様の傾向がみてとれる。強盗致傷では,3年以下の刑期の構成比が,裁判員裁判で16%,裁判官裁判で14%であり,観察付猶予の構成比は,前者で顕著に高い。傷害致死においては,3年以下の刑期の構成比が,裁判員裁判で20%,裁判官裁判で17%であり,観察付猶予の構成比は,差は小さいもののやはり前者で高い。また,強姦致死傷で3年以下の刑期が占める割合をみても,裁判員裁判で7%,裁判官裁判で5%と,差は小さいながら前者で高い(ただし執行猶予を付けた判断の構成比は,裁判員裁判で4%,裁判官裁判で5%であり,後者がやや高い。)。
以上の比較から,3年以下の刑期の構成比に着目する限りでは,裁判員裁判での科刑は裁判官裁判のそれに比べて,寛刑化の傾向にあるといえる。しかし「3年以下」を上回る科刑の状況をみると,判断はまったく違ったものになる。結論を先取りすれば,殺人以外の3罪名においては,寛刑化は刑の下限側だけにみられるものであり,むしろ全体としては重罰化傾向と評価すべき分布になっているのである。3-1-3-10図を丹念にみれば,そのような読み取りは可能だが,ここでは別のグラフ表現にすることで,この点について検討してみたい。
図B〜Eは,それぞれの罪名において,全体のなかであるレベルの科刑をした判決がどの程度を占めるかを示したものである。たとえば殺人を示す図Bをみると,裁判員裁判では80%,裁判官裁判では86%の裁判体で,執行猶予を認めない(すなわち実刑の)判断がなされている。3年以下の実刑を認めず,それより重い刑を求めたのは,前者74%,後者83%,以下同様に,5年以下の実刑を認めなかったのが前者63%,後者69%,7年以下の実刑を認めなかったのが前者49%,後者54%,10年以下の実刑を認めなかったのが前者36%,後者41%である。殺人では刑の程度を問わず,裁判員裁判が裁判官裁判に比べて寛刑化の傾向を示しているとみることができるだろう。これに対して,強盗致傷を示す図Cをみると,執行猶予や3年以下を認めない判断は,裁判員の方が低いのに対して,5年以下,7年以下を認めない判断は,裁判員の方が高くなっている。つまり少なくとも有期刑の中間の領域においては,裁判員裁判に厳罰化の傾向があるということである。傷害致死(図D)や強姦致死傷(図E)でも似たような状況であり,裁判官裁判に比して裁判員裁判で,5年以下,7年以下を認めないという判断がとられやすいことがわかる。10年以下も認めないという重い判決も,裁判員裁判では多くみられており,全体的に厳罰化の傾向があるといえるだろう。
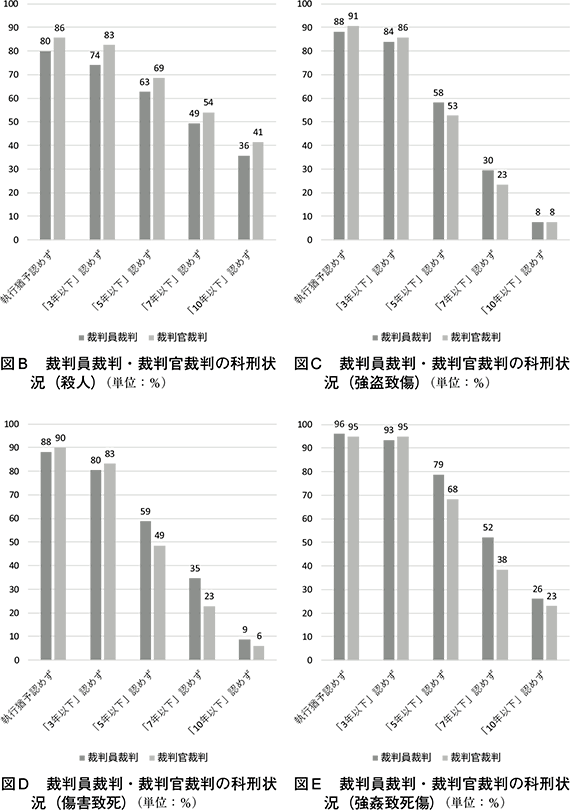
なお,3-1-3-10図の元データ(付録CD-ROM 所収)から,科刑状況(懲役年数)の平均と標準偏差を試算してみた(表F)。この試算では,執行猶予付を0年,3年以下の実刑は3年,5年以下は5年のような要領で求めた値を懲役年数とした。無期は40年とみなし,死刑は試算の対象から除外した。粗い試算なのであくまで参考値としてみるべきであることには留意する必要がある。そのうえで表を読み取るならば,殺人・傷害致死・強姦致死傷では,裁判員裁判で裁判官裁判に比べて,懲役年数が長くなっていると考えられる。また標準偏差からは,裁判員裁判の導入後,殺人では科刑状況のばらつきが小さい方向に変化し,傷害致死では科刑状況のばらつきが大きい方向に変化したと考えられる。
表F 裁判員裁判・裁判官裁判の科刑状況の平均と標準偏差(参考値)
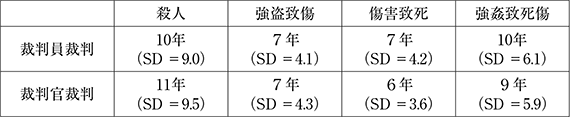
4 犯罪被害調査に基づく分析
本白書第6編「平成における犯罪被害者」は,第1章「犯罪被害」,第2章「刑事司法における被害者への配慮」から構成される。第1章は第1節「統計上の犯罪被害」と第2節「犯罪被害についての実態調査」から成り,このうち第1章第1節と第2章については,いわゆるルーティン部分である。第1章第2節は,法務総合研究所が実施した犯罪被害実態(暗数)調査(以下「暗数調査」と表記する。)の結果が報告されている。
法総研はこれまでに,12年,16年,20年,24年と4回の暗数調査を実施しており,5回目として行なわれた31年(1〜2月)の調査の結果が,この節の内容である。調査が20年と同規模の6000サンプルで行なわれたこと,第4回の24年調査がそれまでの3回の調査とは異なり郵送調査にしていたところ,今回の第5回調査では訪問面接調査(一部は自記式調査)に方法を戻したこと,以上2点を筆者は高く評価したい(訪問面接と郵送では結果が大きく変わるため,24年調査は他の調査と比較することができないと筆者は考える。)。
今次の調査は,世帯犯罪被害,個人犯罪被害,各種詐欺等被害の3パートから成る。6-1-2-1図でその結果が示されている。過去5年間の被害率でみると,世帯単位で被害の有無を尋ねる世帯犯罪被害では,自転車盗(11.4%)がもっとも多く,ついで自動車損壊(8.7%)が挙げられる。個人単位の被害を尋ねる個人犯罪被害のなかでは,「個人に対する窃盗」が2.3%ともっとも高い。
6-1-2-2図では,過去5年間の被害率に関する過去の調査結果との比較が示されている。この図の掲載と結果への言及はもちろん意義があるのだが,筆者は,2つの留意点があると考える。ひとつは先述のとおり,24年調査は調査方法が異なるため単純比較が困難であること,もうひとつは各年の被害率の数値の大小に意味があるか否かを判断するためには,標本誤差を考慮しなければならないことである。
24年調査を除く各回の調査結果に基づき,乗り物盗,車上盗,不法侵入(未遂を含む,以下同じ。),「強盗等」のそれぞれについて,比率の差の検定(多重比較はライアンの方法による。両側検定で,有意水準は5%とする。)を試みてみた。過去の調査結果は,法総研研究部報告10・29・41を参照した(「強盗等」は後述の理由により,16年調査も検討対象から除いた。)。その結果,自動車盗と不法侵入においては,20年>31年の1ペアのみで有意差がみられた。「強盗等」は独立性検定で非有意だった(χ2=1.736,df =2,p=0.420,多重比較は意味をなさない。)。車上盗・バイク盗・自転車盗では,いずれも12年>31年,16年>31年,20年>31年が有意で,これらに加えて,車上盗では16年>20年で,バイク盗では12年>20年で,自転車盗では12年>20年と16年>20年で有意差が認められた。
また,暗数調査は公式統計と相互対照させてこそ,有意義に活用できるのではないだろうか。試みに,乗り物盗,車上盗,不法侵入,「強盗等」のそれぞれについて,31年の暗数調査における被害率(の点推定値)を100としたとき,12,16,20年のそれがいくつになるかを計算した(暗数調査指数)。あわせて,暗数調査の「調査年前年までの5年間」の認知件数の平均値を求め,26〜30年の平均値を100としたときの各期間の値を計算した(認知件数指数)。2つの指数の推移を,犯罪態様別にグラフにしたのが,図G〜Lである(暗数調査の調査票のワーディングに従って,車上盗には部品盗を,不法侵入(刑法犯の住居侵入)には侵入盗を,「強盗等」には恐喝とひったくりを含めた。16年調査のみ「強盗等」
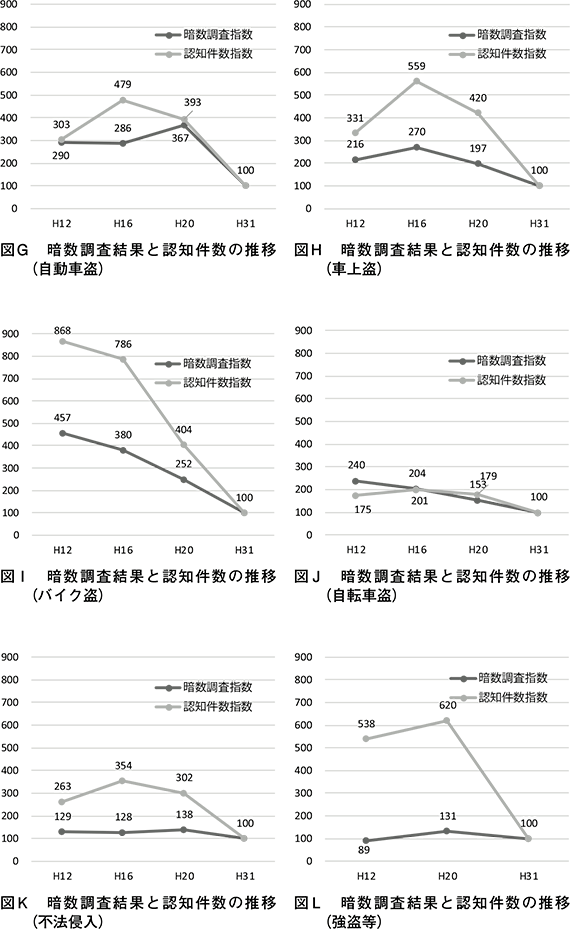
に恐喝とひったくりを含めていないので,この年のデータは比較対象としない。以下本文中では「強盗等」は「強盗」と表記する。)。
これらの図から,複数の犯罪類型において,12年や16年の認知件数が,犯罪実態とは異なる理由で多くなっていることがわかる。たとえば16年に注目すると,強盗では認知件数指数が620なのに対して暗数調査指数は131である。不法侵入では前者が354,後者が128だ。理由のひとつは被害申告率の違いにあると想定されるため,それを参照したところ,強盗も不法侵入も16年より31年のほうが申告率はむしろ高くなっていた。つまり,少なくともこれら2つの犯罪類型についていえば,認知件数が実態よりも多くなったことを,被害を申告する人が増えたという理由から説明することはできないと思われる。紙幅の都合で,これ以上の言及はできないが,暗数調査の結果は,公式統計の解釈にとって重要な手掛かりとなることを,ここでは強調しておきたい。
5 まとめにかえて
以上,平成年間の犯罪・非行情勢と刑事政策の変遷に関するデータブックともいえる本白書のなかから,筆者の関心にしたがっていくつかのトピックを抜き出して,示されている主なデータを紹介するとともに,考えられる別種のデータ提示方法や活用法について述べてきた。エビデンスに基づく政策遂行の重要性への認知が高まった今日においてもなお,犯罪・非行に関しては,エビデンスなき言説が生産され流通され続けているのが現状であり,その意味において,犯罪・非行に関わる各官公庁の統計に基づいて,その中核となる部分を抽出し,それらを有機的・体系的に整理して,わかりやすく国民に示すという役割を担ってきた犯罪白書の意義は,今後ますます大きくなるに違いない。
昭和35年の創刊から数えて,今年度刊行の本白書は,ちょうど60巻目である。これまでの基本的なスタイルを継承していくことが重要なのは,論を待たないが,そのうえで今後は,既存データのイノベイティブな活用方法の提案など,新しい挑戦にこれまで以上に踏み込んでいくことを期待したい。
(京都大学大学院教育学研究科准教授)